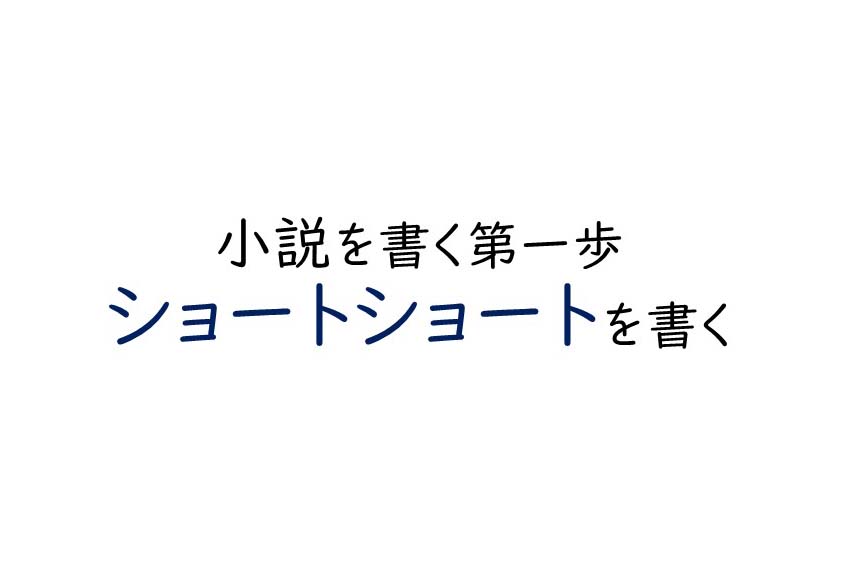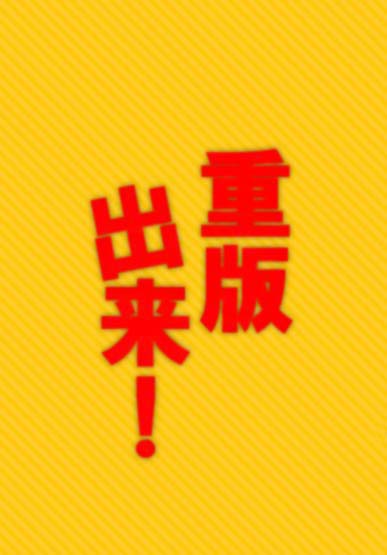意外と今、新人が舞台を書く機会は多いんじゃないかと思います。舞台自体も増えていますし、事務所が若手の役者を舞台で鍛えようという時に、新人作家を舞台に投入しようというのも多くなっています。その他に、自分で書いて上演することもできます。
シナリオ・センターに通っている方は、どちらかというと映像をやりたい方々だと思いますが、舞台にも脚本は必ず存在しているものなので、やっておいて損はないです。
私もまったく舞台のノウハウがないまま始めたので、よく「映像的だ」って言われます。「こんなのどうやって舞台化するんだ」なんてブーブー言われて、すいませんって言いながらやっています(笑)。
アニメーションでは、さきほどの『かぐや姫~』のシーンのような、実写ではとても撮れないようなことが表現できます。一方舞台は、映像では撮れるけど、舞台ではどうやってやるの?っていう想像力を掻き立てるようなことができるのです。
『銀河廃線』は劇団ユニット・テトラクロマットの第1回公演です。キャッチコピーが「あの夜、僕は汽車から降りた」。お察しの通り、「銀河鉄道の夜」をモチーフにしています。それを現代的に解釈しました。
引きこもりのジョバンニと、ろくでなしのカンパネルラが出てきます(笑)。原作では純粋な2人の少年が銀河鉄道に乗って、カンパネルラは実は亡くなっていて、夢が覚めると彼は運河に落ちて亡くなっていて……っていう、要は銀河鉄道とは幽霊列車で、それをモチーフに書きました。
トキという役がジョバンニですね。カンちゃんがカンパネルラ。エリという女の子がザネリ。原作ではザネリは意地悪な男の子がですが、それを女の子にして、彼女は男の子同士の友情に嫉妬して、自分が湖に飛び込んでしまう。
原作でもザネリもジョバンニに意地悪をして、ふざけて運河に落っこちて、そのザネリを助けるためにカンパネルラが亡くなってしまう。この作品でも、湖に飛び込んだエリを助けようとして、カンちゃんが亡くなってしまうという展開です。
エリを助けたあと沈みかけたカンちゃんを、トキが助けようとするんだけど、結局、トキはカンちゃんの手を離してしまう。その封じていた記憶が甦るシーン。「舞台はいつしか湖の中になる」から始まるシーンで、ト書は「トプンという音と共にトキが落ちてくる」。
ありえないじゃないか、どうやって舞台でやるんだと思うでしょう。トキが真実に気が付いて、自分の真っ黒い記憶を思い出して、罪の意識におののいて、どんどん自分の深層心理の中に沈んでいってしまう。
それをカンちゃんが呼び戻す。トキを呼ぶカンちゃんの声が入って、ト書は「トキの腕をつかんだのはカンちゃん。2人、水面へ上昇していく」。それで、カンちゃんが「違うよ、お前が俺の手を離したんじゃない。俺がお前の手を離したんだよ」ってところで、もう1回過去に戻るんです。
映像なら、パッと戻れますが、どう舞台でやるのか。「水面の中から上を見上げるカンちゃん」「カンちゃんとトキの手がつながるが、離れる」。
映像だったらアップにすればちゃんと見せることができます。だけど舞台でこのト書を演出家はどうしたか……。
台本には書いてないですが、演出家は人形を使おうと考えた。人形を動かしていた黒子たちは他の出演者です。人形が溺れる様子っていうのは演技なので、俳優さんに演ってもらいました。
人形と手をつないでいて、離れてしまう瞬間を印象的にするために、皆が手を離す動きをした。やっぱり役者さんじゃないと、余韻のある手の動きはできないので。
この演出家とはこの後も一緒にやっているんですが、私が好き勝手に書くので、いつも怒られます。ちなみに、この『銀河廃線』の最後のト書きは「そこに銀河がある」です(笑)。
第2回の『花の下にて』では、西行法師がゾンビを作ったという話を基にしました。実際に『撰集抄』という古典に、西行法師が高野山にいた時に寂しくなって、荒れ果てた野で人骨を集めてゾンビを作った時のレシピが書いてある。
その話が面白いと思って、そのレシピで(笑)蘇った人斬りが……という話にしました。これもト書の中に「そして、骨になる」って書いてあります(笑)。このト書をどうするんだと、ワイワイ言いながらやりました。
演劇っていうのは、「どうするんだ」から始まり、演劇ならではの手法を使うことによって、思いのこもった表現ができるんです。脚本家の思いもよらないところで表現してくれる。それが面白いところだと思います。
3回目は『風は垂に吹く』という、どちらかというと『銀河廃線』のようなファンタジックな作品です。今回は「そこに雲が広がる」って書きました(笑)。今回はグライダー、エンジンのない飛行機の話です。
私が「城戸賞」をいただいた作品もグライダーの話ですが、中身はまったく違います。グライダーを素材にして舞台にしようよという話になりました。