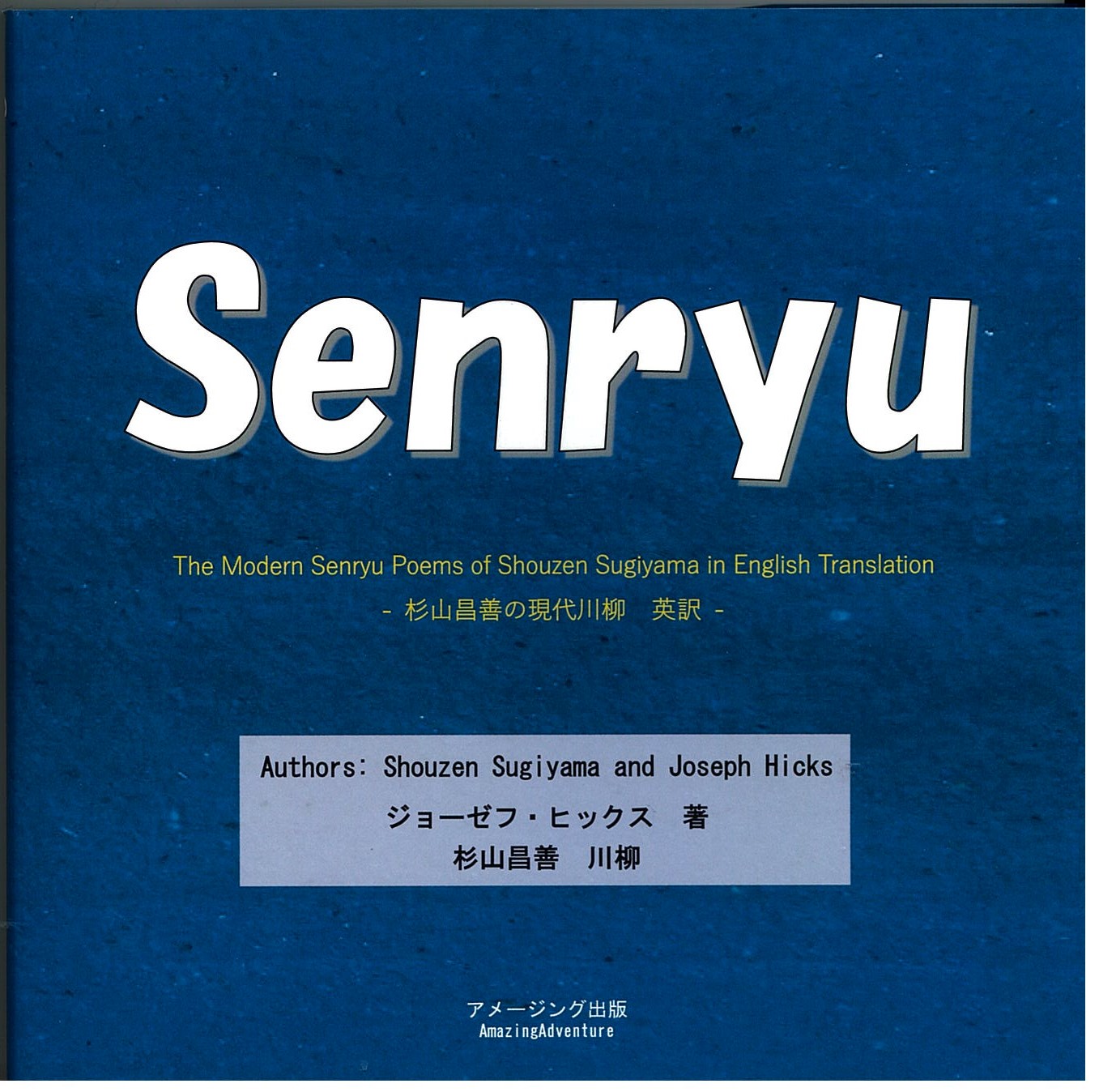暗黒時代
シナリオ・センター代表の小林です。地震に大雨、コロナだけでなく、日本は災害大国なのだということを、イヤというほど実感させられた先週末でした。
東日本大震災から10年経とうとしていますが、人の心の傷は一生癒すことはできませんし、復興というには程遠い10年目に、私たちは本気で災害というものを見据えていかなくてはいけないように思います。
少しずつコロナ感染者の人数は収まってきている様子に見えますが、感染者の自宅待機はまだ1万人以上もおり、医療の逼迫は決して緩和されていないとのこと、こんな時にまた大地震が来たら・・・。
もちろん危機管理は徹底してできているのですよね。お上の皆様。ね、ね、ねぇ!
それにしても、2020年代は、暗黒の時代として歴史に残りそうですね。
日本は、女性蔑視、東京五輪・パラリンピック組織委員会会長の後継者、菅首相の息子さんの賄賂、河合議員の自民党本部からの買収資金問題など、今だけでも問題山積ですが、コロナに加えて、今までろくでもないことをやってきたツケがこれほど回ってきたことはなかったのではないでしょうか。
ああ、そうだ、モリカケサクラも終わっていないのでした。
なかなかいいことは見当たりませんが、悪いことの後にはいいことがあるはず、そう信じて、もうひと踏ん張りしましょうか。
暖簾にひじ鉄
2/19号の週刊朝日の内館牧子さんのエッセイ「暖簾にひじ鉄」で、シナリオを学んだ頃のお話を書いてくださいました。
シナリオ・センターへ通おうと思っていた頃は、女はモノの数に入れない時代だったと時代背景を書いていらっしゃいます。
本当に、今問題の女性蔑視以前、モノの数に入らない、存在さえなかったいう時代だったのです、女性は。わずか40年前の話しです。
私は、当時コピーライターをしていたのですが、某大家電メーカーの宣伝課長に担当になったご挨拶に行ったところ、「え~、なに、女の子なの、女の子は困るな~。すぐ泣くし~」と言われ、泣いてやろうかと思ったことがあります。(笑)
こうした男性社会の女性に対する見方が、今も脈々とあるからこその森前会長の発言、根本が変わらないと何も変わらないと思います。
そんな時代を経て、内館さんはプロの脚本家となっていきます。
あの内館牧子さんですら、脚本家が作家の一種だと知ったのは、シナリオ・センターに入ってからで、脚本家は原作の書籍をシーンで割る職人だと思っていたそうです。
映画も見たことなく、小学校の校庭で幕張っての映画会でみた「若乃花物語・土俵の鬼」で本物の若乃花がシロウトなのにセリフが言えるのが凄いと思ったくらいのドシロウトぶり。
なんだか安心しますよね。
でも、でも、です。
何も知らずに入られた内館さん、そこからが凄い。
「あなた、これから映画を観なさい。片っ端から見て、映画ノートをつくる。そこからね」と講師に(言ったのは後藤所長です(笑))言われて、会社勤めしながら年間250本くらいみられたそうで、レンタルビデオもDVDもない時代にです。
内館さんは、その後ドラマ誌で募集していた「第4回ドラマ新人賞」に応募し、「春のつむじ風」で佳作をとり、そこからNHKのプロデューサーが行う新人脚本家養成のメンバーに、その縁で橋田寿賀子さんのおそばで資料整理のお手伝いなどをして・・・少しずつ脚本家の階段を昇り始めるのです。
エッセイの本質上、エッセイを切り取って例にとるのは、たいへん失礼なことだと思うのですが、内館さんのような大御所でも、40年前は何も知らないシロウトだったということ、でも、やるべきことをやればプロになるのだということを、皆さんにお伝えしたいと思いました。内館さん、ご容赦を。
内館さんは「シナリオ・センターで勉強したことと映画を見続けたことだけを頼りに、脚本を書いた」とおっしゃっています。
映像技術の基本をしっかりと身につけること。他人が創った作品から客観的に学ぶことは、とても大事なことです。
「何も知らないことは悪ではないが善ではない」という言葉がありますが、家にいることが多いこのコロナ禍の時期では、本を読む時間、ドラマやDVDを見る時間ができるということは、創作者にとっては幸運なことだと考えて、有効に時間を使い、創作の引き出しをいっぱい作っておきたいものです。
内館さんのエッセイを、週刊朝日2/19号で楽しまれたら、月刊ドラマの2月号にロングインタビューとして掲載されていますから、そちらも読んでいただければと思います。