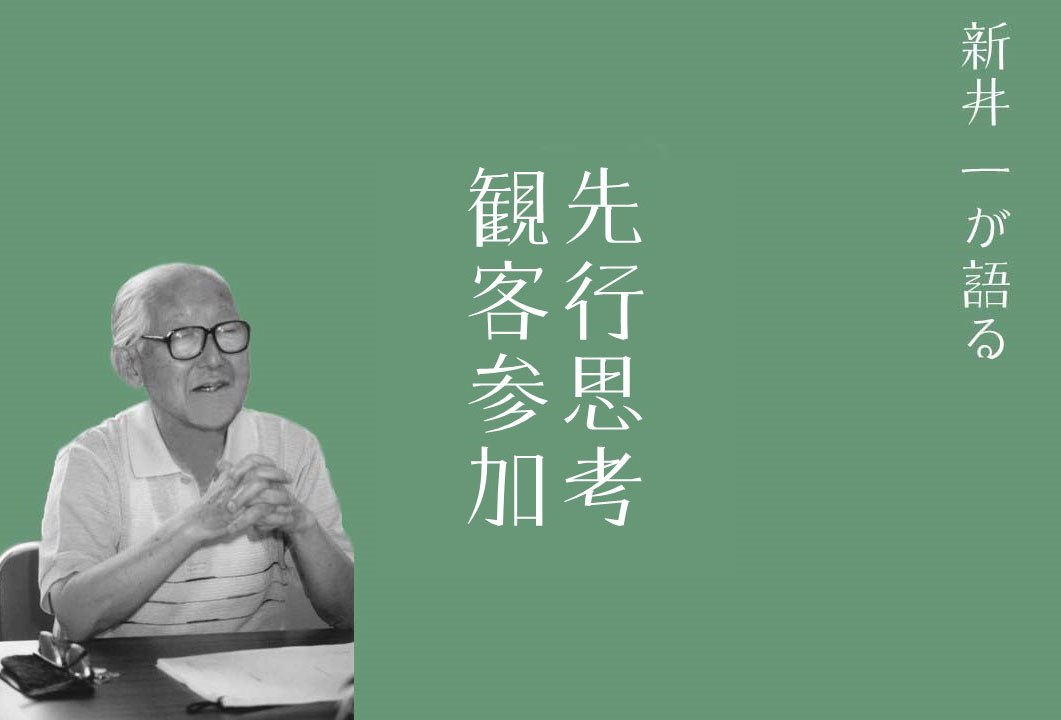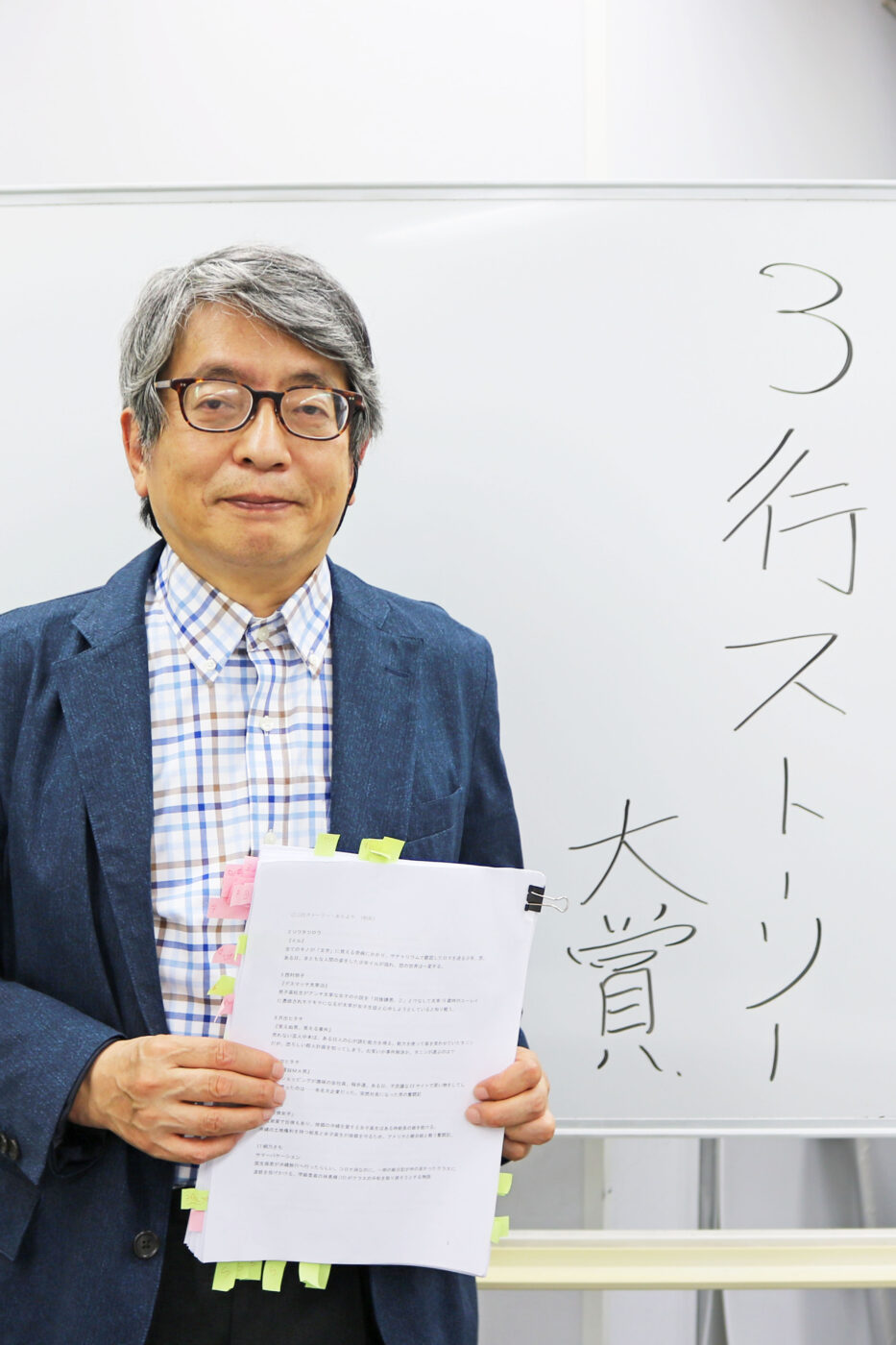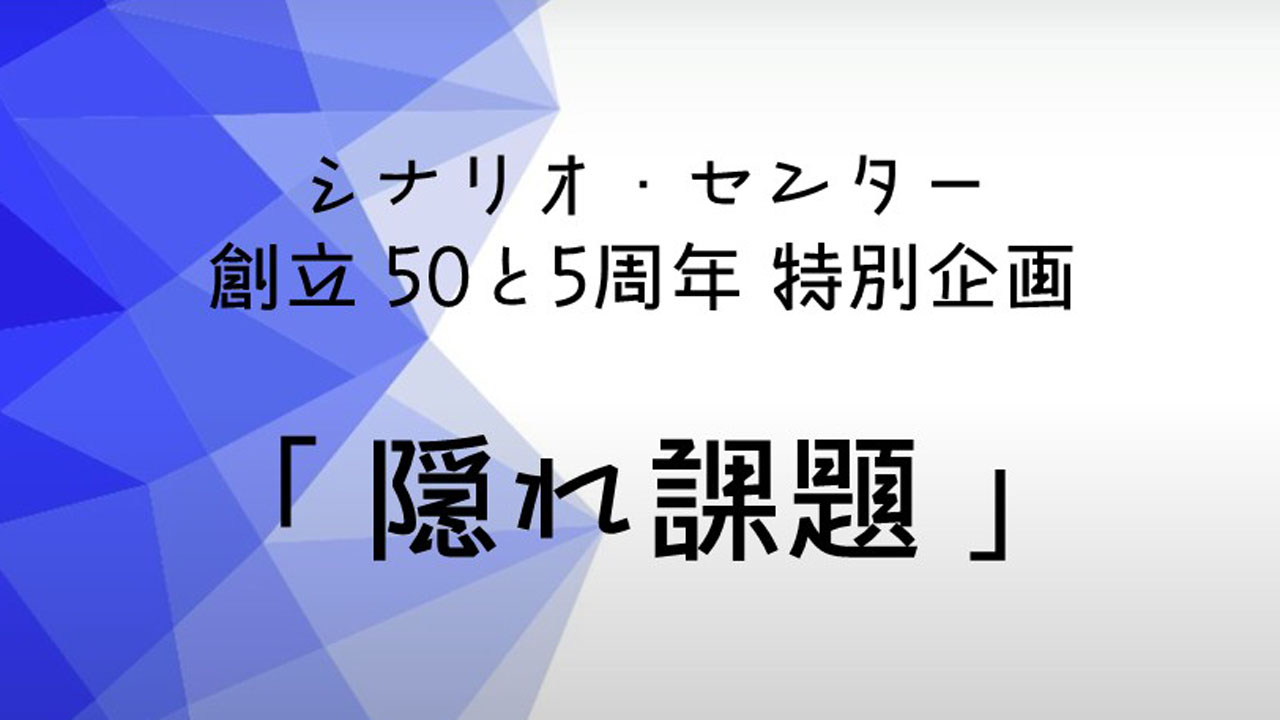脚本家でもあり小説家でもあるシナリオ・センターの柏田道夫講師が、公開されている最新映画を中心に、DVDで観られる名作や話題作について、いわゆる感想レビューではなく、作劇法のポイントに焦点を当てて語ります。脚本家・演出家などクリエーター志望者は大いに参考にしてください。普通にただ観るよりも、勉強になってかつ何倍も面白く観れますよ。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その43-
『ドライブ・マイ・カー』人物たちが本音を明らかにする時
カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞、約3時間という長尺ながらロングラン上映されている『ドライブ・マイ・カー』です。
原作は村上春樹の同名短編小説などで、脚本は濱口竜介監督と大江崇充さんの共同。濱口監督は15年の『ハッピーアワー』(上映時間5時間以上!)で注目され、18年『寝ても覚めても』(これは約2時間)で商業映画デビュー。大江さんは俳優や演出の舞台経験を経て、『適切な距離』などインディペンデント映画の脚本・監督ということ。
通常(商業映画の場合)3時間という長さの脚本の映画化は難しく、脚本家志望者の見本にはなりにくいのですが、この映画が醸し出す世界やテーマ性、すなわちそれを導いている脚本の造りは大いに参考になります。
私自身、観る前に「3時間か」と構える気分で臨んだのですが、少しも長いと感じませんでした。それどころか、まさに主人公、家福悠介(西島秀俊)のあの赤いクルマ(スウェーデンのサーブ900だそうだ)にゆったりと同乗しているような豊かな心地よい映画的時間を過ごしました。
家福は名の通った舞台役者兼演出家で、妻の音(霧島れいか)は脚本家。二人は共に物語を紡ぎ合う関係であり、確かに深く愛し合っているのですが、家福は妻の秘密を知り、しかも突然死されてしまう。
喪失心を抱えたまま、家福は広島の演劇祭の演出をすることになり、専属ドライバーがあてがわれる。無口ながら運転技術の高いドライバーの渡利みさき(三浦透子)と家福は、サーブ900でのドライブ時間を共有し、次第に互いの傷を見せ合うことで、生きている人間として新しい時間(未来)を見いだしていく。
この二人に、妻の不倫相手の一人であった俳優の高槻耕史(岡田将生)も加わって、心理模様が複雑にからみます。
前回のこのコラム(※)では、バックステージもの、劇中劇を巧みに活かしている『サマーフィルムにのって』を取りあげました。
本作では最初は『ゴドーを待ちながら』で、上演予定のチェーホフの『ワーニャ伯父さん』が、劇中劇として役者たちのオーディションから本読み、稽古と進み、物語の進行と合わせてかなり綿密に描かれます。それも韓国語や手話など、いくつもの言語で演じられるという試みまで。
そうした構成の妙もですが、今回特に見てほしいのは、人物の過去や心の内、本音のあかし方、告白のさせ方についてです。
家福はあてがわれたドライバーのみさきを、最初は受け入れようとしません。見るからに若い女で愛想もない。実際にみさきは寡黙で、問われることに応じるだけで、余計な会話は送り迎えの間もなされません。
そうするとセリフのやりとりがなくなり、場面として持たないのですが、家福がセリフの練習のために、亡き妻の音声の入ったカセットテープが流される。この抑揚をあえて抑えた音の声が、絶妙に時の流れを作る。
家福の喪失感はそれまでに描かれているので、観客にはそれなりに分かっているのですが、どう感じているのか、といったことは簡単に語られない。みさきがなぜドライバーとしての技術に長けているのかは、途中で語られるのですが、彼女のトラウマ的な過去は【転】でようやく分かる構成になっています。
初心者のシナリオの欠点として、いとも簡単に主人公や脇役が、本音とか過去のトラウマとかをべらべらと喋ってしまう、というのがあります。
もちろん尺もあって、さっさと分からせないと先に進めないという作者の都合もあったりするのですが、何の葛藤もなく心の内をセリフにしてしまうと、いかにも「それってかる~いよ」「説明している」と感じてしまう。自分に置き換えてみてほしい。人は初対面の他人とかに身の上とか本音とか、いきなり語らないでしょ、と。
『ドライブ・マイ・カー』の二人の会話の過程をじっくりと読み取って下さい。どういう時間を経て、どういうきっかけがあると、人は他人に本音を吐露するものなのか。ちなみに回想シーンもありません。
役者さんたちが皆素晴らしく、そこも見どころなのですが、特にみさきを演じている三浦透子が素晴らしい。来年の助演女優賞は間違いないでしょう。
※映画『 サマーフィルムにのって 』のコラムはこちらから
https://www.scenario.co.jp/online/28687/
YouTube
シネマトゥデイ
映画『ドライブ・マイ・カー』90秒予告
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その44
『MINAMATA―ミナマタ―』一枚の写真(映像)こそが最大の武器になる
ジョニー・デップが主演のみならず、プロデューサーとしても参画した話題作『MINAMATA―ミナマタ―』です。
ごく稀にですが、映画が始まってファーストシーンのファーストカットで、心が鷲掴みされる感動を覚えることがあります。その瞬間に「あ、この映画は素晴らしい」と思えてしまえる。
本作のファーストカットは、クライマックスのある場面のほんの1分くらい(もっと短いかも)の断片ですが、かすかに囁かれる子守唄と、美しい女性の横顔、続く衝撃で、一瞬にして涙がこみ上げそうになりました。
ついでですが、この女優さんは岩瀬晶子さん。脚本を書いた『二宮金次郎』で、金次郎の母役をやって下さった方だと気づいて感慨ひとしおでした。
ジョニー・デップが演じたのはフォトジャーナリストのユージン・スミス。1970年代、アル中でボロボロの晩年を送っていた彼に、日系人のアイリーン(美波)が、当時日本で問題となっていた水俣病の写真を撮るように依頼する。彼女は後に、ユージンの伴侶となるのですが、【起】はアイリーンとの出会いやユージンの現状と、水俣へと向かうまで。
私ごとですが、私の父は写真が趣味で、家には写真雑誌や世界中の写真家の写真集があって、子どもの頃からそれを見て過ごしました。
ユージン・スミスの名は二枚の写真で記憶に刻まれていました。その一枚は冒頭部でチラと映る、二人の幼子が木陰のトンネルを抜けようとしている「楽園へのあゆみ」で、もう一枚こそがファーストカットでもあり、水俣病の象徴ともなった「入浴する智子と母」でした。
この写真と半世紀ぶりくらいに再会したような気持ちと、どのような経緯で撮られたか、という物語をようやくつぶさに知りました。映画によって今さらながら教えてもらったわけで、これも映画の素晴らしい効用です。
それはともかく、今回見てほしいのは、シナリオの原点中の原点ともいえる“映像の力”です。
すでに過去の栄光であろうと、ユージン・スミスは著名な写真家であり、彼が水俣病を写真に撮り、それを世界に発信できれば世論を喚起できる。
ユージンとアイリーンは3年もの間、水俣に住み写真を撮ります。その間、水俣では、さまざまな動きがあった。有機水銀を海に垂れ流していた企業「チッソ」からのユージンへの取り込み工作や、一転の妨害。反対派内部の分裂やチッソとの交渉、闘争……
そうした経緯を経て、ユージンは被害者自身を写真におさめるために語る。「1000の言葉に一枚の写真が匹敵することがある」と。
こうした実在した人物の物語、さらには社会派ドラマとして、巨悪や権力の告発といったテーマを追求しようとすると、どうしても言葉(セリフやナレーション)で語ろうとしてしまいます。
そうした要素もあってもいいのですが、やはり映画は映像なのです。最後にたどり着いた一枚のユージンの写真が、世界中の人の心を掴み、世の中を動かしたように。
この映画の監督はアンドリュー・レヴィタス。このコラムでは8回目に取り上げた『ホワイトクロウ 伝説のダンサー』(※)の監督でした。
撮影はブノワ・ドゥローム。ベトナム発の名作『青いパパイヤの香り』や、スティーブン・ホーキング博士と妻の物語『博士と彼女のセオリー』などのキャメラマン。いくつもの美しいシーン、特に被害患者ら家族の姿や、ユージンとのふれあい。これらいくつもの場面を、見ているだけで涙が出ます。
そうした映像こそがなによりも観客への言葉、メッセージとなる。ここで描かれた水俣の問題さえもまだ解決しておらず、それどころか3.11の福島原発事故を筆頭に、同系の社会問題はその後も世界中で続いている。
そうしたテーマ性を訴える手段として、報道としての一枚の写真や、映画というフィクションがどれほど有効か、ということも教えてくれます。
主演の二人はもちろん、真田広之、加瀬亮、浅野忠信、そして敵側でもある國村隼ら俳優さんが皆素晴らしかったことも述べておきます。ぜひご覧下さい。
※『ホワイト・クロウ 伝説のダンサー』のコラムはこちらから
https://www.scenario.co.jp/online/24077/
YouTube
シネマトゥデイ
ジョニー・デップ主演『MINAMATA(原題)』海外版予告編
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。