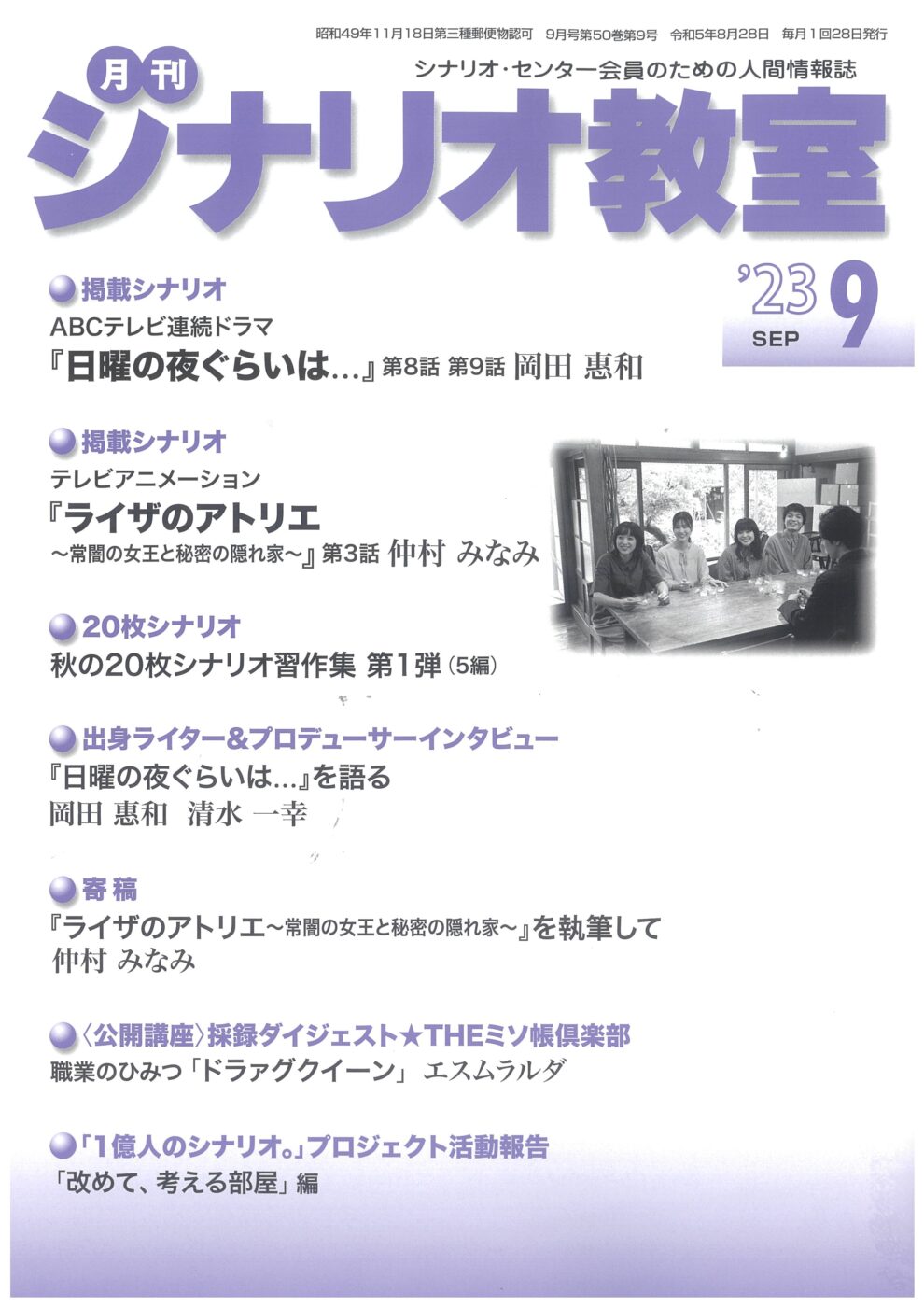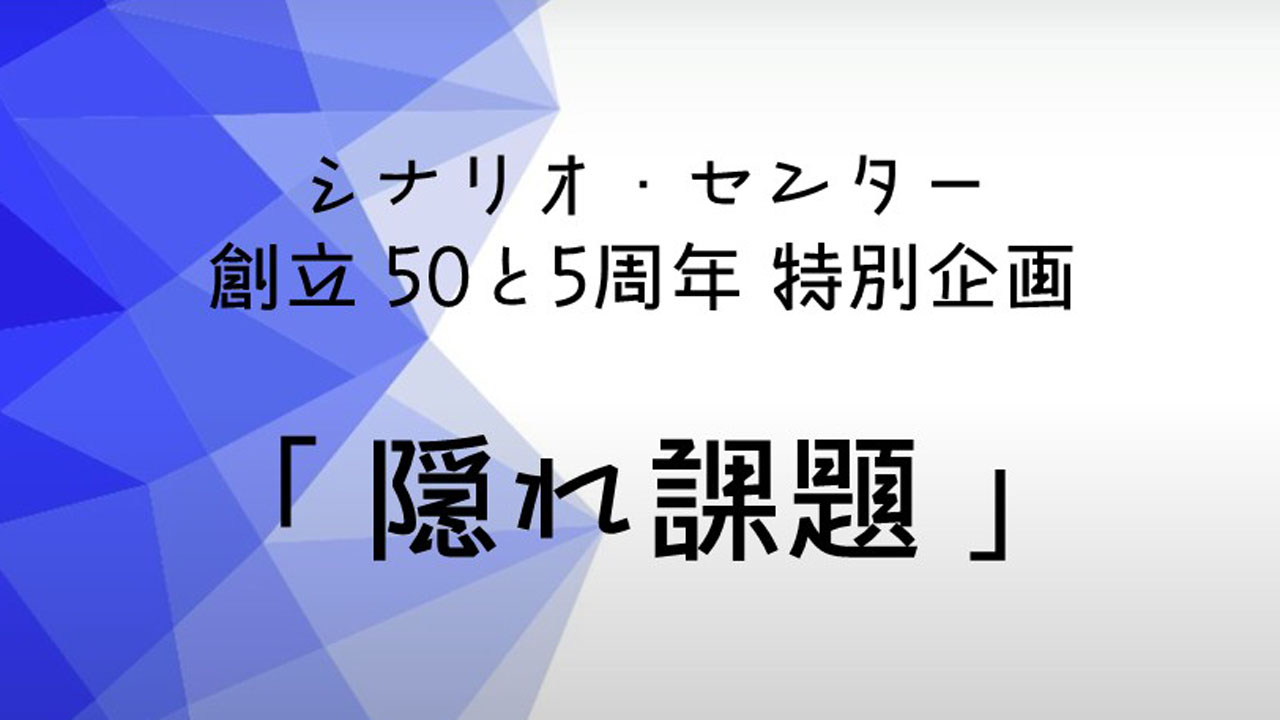脚本家でもあり小説家でもあるシナリオ・センターの柏田道夫講師が、公開されている最新映画を中心に、DVDで観られる名作や話題作について、いわゆる感想レビューではなく、作劇法のポイントに焦点を当てて語ります。脚本家・演出家などクリエーター志望者だけでなく、「映画が好きで、シナリオにもちょっと興味がある」というかたも、大いに参考にしてください。普通にただ観るよりも、脚本の勉強になって、かつ、何倍も面白く観れますよ。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その75-
『CLOSE/クロース』陰影シーンの作りと、少年たちの輝きを見逃すな!
今回の作品は、カンヌ国際映画祭コンペティション部門でグランプリをとった『CLOSE/クロース』です。共同脚本(もう一人はアンジェロ・タイセンス)・監督は、一作目の『Girl/ガール』でカメラドール(新人監督賞)をとったルーカス・ドン。ベルギー生まれのまだ32歳の新鋭です。
いわゆる少年(キッズ)ものですが、このコラムでは過去にも26回の『mid90s ミッドナインティーズ』(※)や、55回の『ベルファスト』(※)など、何作か取り上げていました。
『ベルファスト』は、北アイルランド紛争という社会性が背景になっていました。『mid90s』の主人公スティーヴィーは、『クロース』の二人の少年レオ(エデン・ダンブリン)、レミ(グスタフ・ドゥ・ワエル)と同じ13歳!
ここでも書きましたが、性にまだ目覚めるような目覚めないような、微妙な思春期の一時期なわけで、それはまさに珠玉の輝きが放たれる人生の一瞬ともいえる年齢だったりします。ゆえにこうした少年ものは、ノスタルジー色が似合ったりします。『mid90s』も『ベルファスト』もその味わいでした。
しかし『クロース』には、こうしたノスタルジー色はありません。監督自身の少年期の体験、思いが発想にあったそうですが、むしろ今の少年期特有の痛みがひしひしと伝わる映画になっています。
ちなみにタイトルは、“親密な友情”という意味合いの“close friendship”から来ているとのこと。
さて、今回の「ここを見ろ!」は、このメインテーマでもある少年期の痛みなり哀しみを描くためのメリハリ、陰影の作りです。レオとレミは、いつも一緒にいる幼なじみの親友です。冒頭からこの二人のまさに輝くような時間を、丹念に綴っていきます。
予告編にもありますが、花畑を二人で疾走するシーン、自転車で並走するシーンの輝き、美しさ、二人で密着して眠っているシーンの微笑ましさ。当たり前のように仲がいい二人なのですが、彼らが社会である中学校に進学することで、関係性に微妙なズレが生じていきます。
二人の自然な仲のよさに、クラスメイトの女の子からは「あなたたちはカップルなの?」と尋ねられるし、男の子からは、ゲイじゃないか、とからかわれてしまう。思春期の男の子である二人にとって、そう見られることは心外です。彼らは普通にずっと一緒に、兄弟のように、まさに“親密な”仲がいいだけなのですが、社会はそれを許さずカテゴライズしようとする。
中盤以降に、大きな展開が待ち受けているのですが、それはぜひ映画を見て確かめて下さい。そこからズキズキと突きつけられる少年の痛み。前半部の陽としてのいくつものシーンがあることで、陰である後半が際立つ作りになっています。
ちなみに、この映画にはいわゆる回想シーンがありません。特に後半部分とかに、回想で過去や前半のシーンを入れたくなりますが、そんな説明を加えなくても、心情が切々と伝わります。
もうひとつ、ぜひこの映画で見てほしいのは、少年役の二人です。レミ役のグスタフ君は、繊細さと無垢さでまさにガラス少年のようです。一方レオ役のエデン君の美しさ。時々ショートカットの美少女にも見える整った顔立ちと、見つめる眼差しの透明さ。二人ともオーディションで選ばれてのデビュー作ですが、今後、大スターになる予感を観客に抱かせます。ちょっと大げさな言い方になりますが、その記念碑的な映画の目撃者にぜひなってほしい。
特にエデン・ダンブリン君。
かつて名匠ルキノ・ヴィスコンティの『ベニスに死す』で、死にゆく老人が、ひたすら見つめる美少年役がビョルン・アンドレセンで、『世界で一番美しい少年』というドキュメンタリーも出来たりしました。あるいは、少年ものというと欠かせない『スタンド・バイ・ミー』には、23歳で急逝したリヴァー・フェニックスが輝いていました。
この二人は鮮烈さゆえに、悲劇的なその後になってしまったのですが、『クロース』のエデン君とグスタフ君の未来には幸あれ、と祈りたくなります。
※YouTube
Klockworx VOD
『CLOSE/クロース』|本予告
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その76-
『高野豆腐店の春』物語の「天・地・人」と「恋は走らせろ!」
今回の作品は、公開講座にお呼びする三原光尋監督の『高野豆腐店の春』です(“こうやどうふてん”ではなく、“たかのとうふてん”です)。
三原監督は、主人公の高野辰雄を演じた藤竜也さんとは、村の写真館の主の話『村の写真集』と、中華料理店の料理人の物語『しあわせのかおり』と、すでに2作品でタッグを組んでいて、本作は職人シリーズ3作目とのこと。三原監督が書いた脚本を藤さんに送ったら、わずか二日後に「ぜひ出たい」という返事を頂戴したそうです。舞台となる街が尾道と決まった時も、ロケハンに藤さん自身も参加されたとか。
このコラムの67回で取り上げた『ひみつのなっちゃん。』(※)も、田中和次朗監督が書いた脚本を読んで、滝藤賢一さんが出演を快諾し、企画にGOサインが出た。俳優さんが脚本に惚れ込んでくれるというのは、脚本家(監督)冥利に尽きます。そういう脚本を書くことが、映画化実現の可能性を拡げるわけです。
さて本作は、尾道で小さな豆腐店を営んでいる辰雄と、その娘の春(麻生久美子)の父娘の物語。
尾道というと、映画ファンの聖地ですね。まず浮かぶのは大林宣彦監督の『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』の尾道三部作ですが、もうひとり『東京物語』の小津安二郎監督もいます。小津作品というと、娘を嫁がせようとする父親との物語『晩春』『麦秋』『秋刀魚の味』といった名作が思い出されます。
いわば永遠のテーマでもあるのですが、本作は「実は、」という父娘にまつわるいくつかの過去も秘められていて、感動的なヒューマンドラマになっています。
それも含めての今回の「ここを見ろ!」は、発想や物語のベースを確かにするための「天・地・人」を固めること。簡単にいうと天(いつ)地(どこで)人(誰が)なのですが、より細かいところまで設定することが、脚本のベースのみならず方向性を決める。その格好の教科書が本作です。
まず「天」ですが、冒頭で“平成の終わる頃の話”と字幕で示されます。なぜ“今”ではないのか?その理由は途中で明らかにされます。
そして「地」は広島県尾道市で、もちろん「人」の履歴でもある豆腐店が主要舞台です。これに商店街仲間の床屋さんや定食屋さん、渡し船が行き来する海峡や、お馴染みのお寺、坂道といった空間も重要な「地」です。
そして「人」は、辰雄と(出戻って50歳にならんとする)娘の春、さらには辰雄の恋の相手・中野ふみえ(中村久美)といった人物たち。こだわりの豆腐を頑固に作り続ける辰雄の職人気質というのも、主人公の性格づけです。これらの作りこそが、人間ドラマを生み出すわけです。
ファーストシーン。豆腐店の早朝、辰雄と春によって作られる豆腐作りの過程を映し、出来上がった豆乳を二人で飲むまで。そしてここでメインタイトル。
このコラムの27回『罪の声』(※)で、アバンタイトルの入れ方について述べましたが、本作も素晴らしい導入で、ここだけで「いい映画なんだ」と分かります。加えて、高野豆腐店のお豆腐のおいしそうなこと。
もうひとつ見てほしい場面があります。父と娘の物語なのですが、述べたように辰雄とふみえの恋の物語でもあります。
で、私は常々 基礎講座などで「恋は走らせろ!」理論を唱えています。恋愛物においては、恋を成就させるために今、この時にこそ、人物を必死にさせる場面を作ること。その具現化として人物を走らせろと。
『卒業』ならダスティン・ホフマンは結婚式場に向かって、ガス欠のアルファロメオを捨てて走る。『アパートの鍵貸します』のシャーリー・マクレーンは、この人こそ、と確信してジャック・レモンのアパートに走る。『初恋のきた道』のチャン・ツィイーは、賢明に作った餃子の鍋を持って野を越え丘を越えて走る。『ラヴソング 』のマギー・チャンは、タイムズスクエアの雑踏を、自転車のレオン・ライを追いかけて走る走る。
名作恋愛物には、必ずそうした場面があります。そして本作。まさにここだよ、という場面で藤さんだけでなく、麻生久美子さんともう一人の彼も走ります。この場面で私は不覚にも涙が止まりませんでした。
それだけでなく、ラストシーンこそもう涙涙涙。日本映画に、さらなる親子愛と老いらくの恋の名作誕生です。
※YouTube
東京テアトル公式チャンネル
映画『高野豆腐店の春』本予告(30秒)
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。