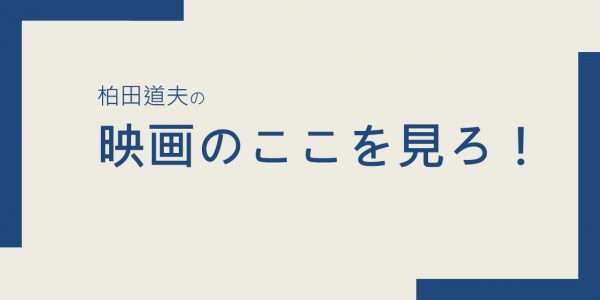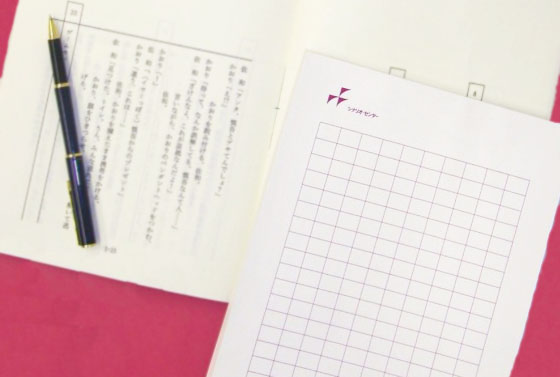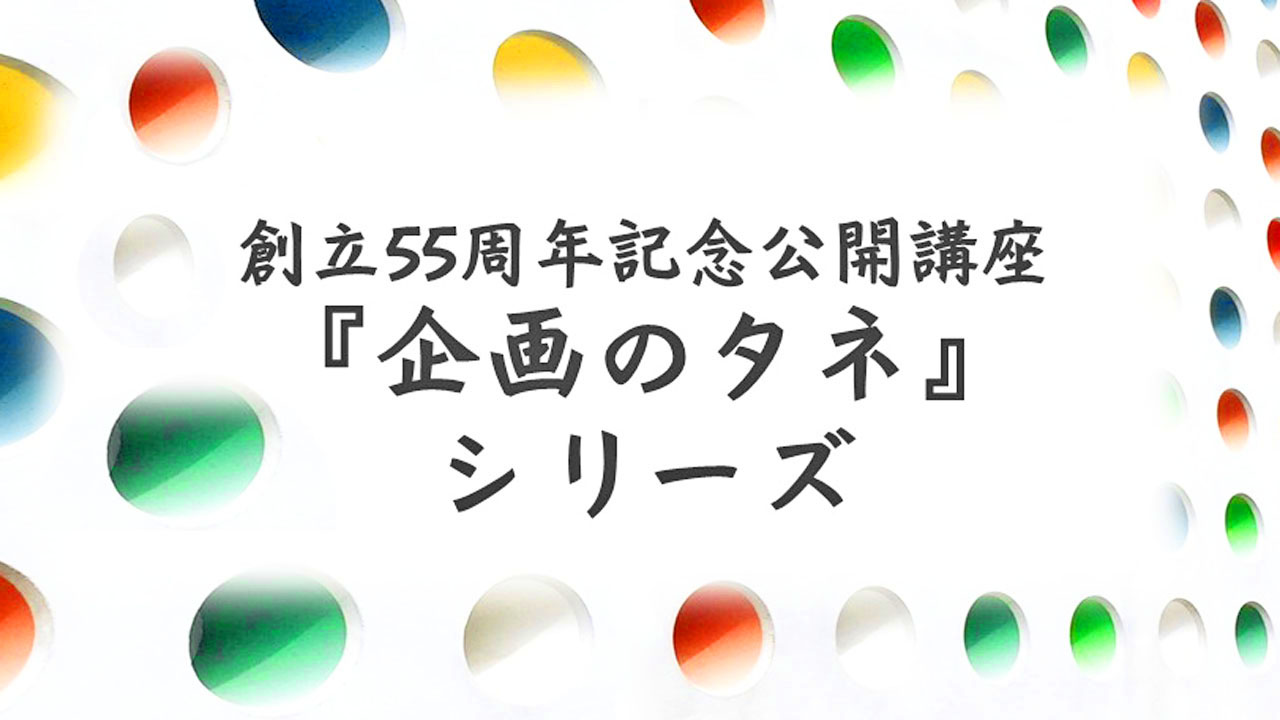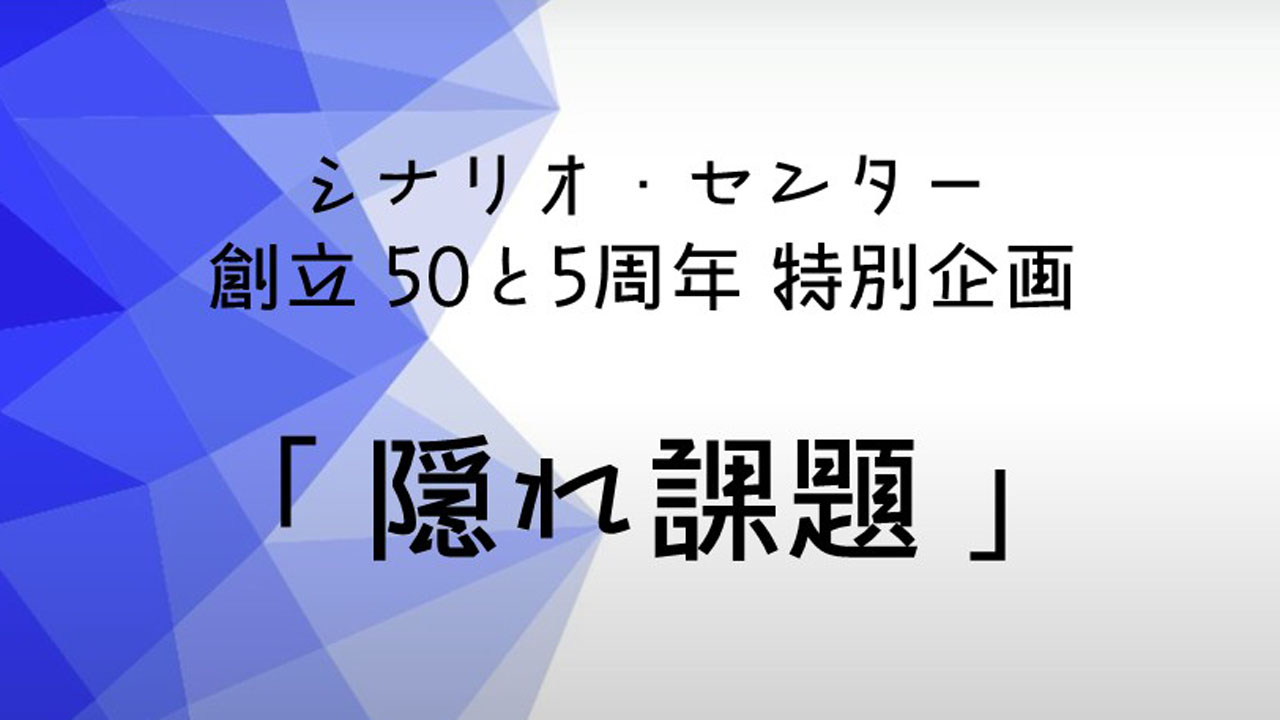脚本家でもあり小説家でもあるシナリオ・センターの柏田道夫講師が、公開されている最新映画や、DVDで観られる名作や話題作について、いわゆる感想レビューではなく、作劇法のポイントに焦点を当てて語ります。脚本家・演出家などクリエーター志望者だけでなく、「映画が好きで、シナリオにも興味がある」というかたも、大いに参考にしてください。映画から学べることがこんなにあるんだと実感していただけると思います。そして、普通にただ観るよりも、勉強になってかつ何倍も面白く観れますよ。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その93-
『ドリーム・シナリオ』ありふれた「夢」が、まったく新しいアイデアになる
ちょっと(どころか、かなりというべきか?)変わったファンタジースリラー『ドリーム・シナリオ』を取り上げます。
ジャンルを“ファンタジースリラー”としましたが、それも違うように思います。映画の紹介ページとかには“スリラー”とあって、確かに後半にいささか怖い場面になったりするのですが、前半はむしろコメディです。
予告編を見ていただくと、この映画の設定が分かりますし、実際にホラーテイストなシーンも登場します。でもそうした範疇におさまらない、やっぱりかなり変な映画で、でもバツグンにおもしろい。
脚本・監督は『シック・オブ・マイセルフ』のクリストファー・ボルグリ。製作会社は異色作を世に送り出し続けているA24、製作に名を連ねているのが、かの傑作ホラー『ヘレディタリー/継承』や『ミッドサマー』のアリ・アスター。このチームで当たり前な映画となるはずはありません。
ニコラス・ケイジ扮する大学教授のポールは、妻と二人の娘を愛するごく平凡な中年男。そのポールがなぜか、知人や学生たち、さらには一度も会ったことのない人の夢に現れるようになる。ポールが現れる夢を見たという人の数は加速度的に増えていき、彼は有名人になってしまい、生活も大きく変わっていってしまう……。
人間が眠っている間に見る「夢」は、つくづく不思議です。フロイトやユングといった専門家が解析したりしていますが、やはり分かるようで分からない。
こうした「夢」は映画ではおなじみで、人物(観客)が見ていて「あ、夢だった」みたいなシーンは繰り返し使われます。
あるいは「夢」そのものを描いた映画もあって、黒澤明監督は晩年にオムニバスで、さまざまな『夢』を映像シーンとして描きました。
あるいは他者の夢に入り込む『インセプション』や『ザ・セル』、日本のアニメ『パプリカ』、夢から殺人鬼が現れる『エルム街の悪魔』というように。
ただ、本作のように、ある一人の人物が、赤の他人の夢に次々と登場してしまう、という話はこれまでになかったはずです。誰もが見る当たり前の「夢」をネタにしつつ、これまで誰も思いつかなかった画期的な(まさにコロンブスの卵的な)アイデアといえるわけです。
さて、そうした画期的アイデアが浮かんだとして、それをどう物語としてのカタチに落とし込むか?その手法こそが、今回の「ここを見ろ!」です。
こうした突飛なアイデアのまとめ方としては、第33回に『ビバリウム』というファンタジー映画で述べていました。これもかなり変わった設定でした。この『ビバリウム』では、こうした一風変わったアイデアの映画として、『トルゥーマン・ショー』と『主人公は僕だった』の二作も例としました。
今回『ドリーム・シナリオ』を見ていて思い出したのは、スパイク・ジョーンズ監督のデビュー作で、奇才チャーリー・カウフマン脚本の『マルコヴィッチの穴』です。怪優として知られるジョン・マルコヴィッチの頭の中へと通じる穴があって、そこから彼の頭脳に入ることができるようになって……。よくまあ、そんな奇想天外な設定を思いついたな、というアイデアの映画です。配信とかで見られるようですので、ぜひ。
ともあれ『ドリーム・シナリオ』ですが、ポールにしてみれば、どうして他人の夢に自分が登場するのかが分からない。彼には何の責任も落ち度もないのに、どんどん困った事態へと追いやられてしまう。
そうした「夢」がどのような「現実」を作っていくか?まさに今のネット時代にも通じる物語の展開のさせ方を見てほしい。
それにしても、この映画の主役がニコラス・ケイジであるというおもしろさ。『マルコヴィッチの穴』は、そのタイトルが示すように、ジョン・マルコヴィッチでなくては成立しなかったそうです。
ニコラス・ケイジは有為転変の人生を歩んでいます。どんな映画にも出演する俳優としても知られていました。まさにどこにでも顔を出す、という彼をこの役にキャスティングしているというおもしろさ。
それにしてもアイデアは尽きません。最初に思いついた人のモノなのですが、実は問題は、それを物語というカタチに落とし込む技だったりします。そこをじっくりと盗みとってほしい。
▼YouTube
Klockworx VOD
映画『ドリーム・シナリオ』予告編
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その94-
『おんどりの鳴く前に』秀逸なモチーフでミステリーに箔をつける
今回はミステリー映画『おんどりの鳴く前に』を取り上げます。
3月3日〆切の「第25回テレビ朝日新人シナリオ大賞」の課題が「ミステリー」。ちょうど今公開中の本作は、「なるほど、こういうアプローチもありだな」と思わせてくれる異色のミステリーです。
その内容をご紹介する前に、本コラムでは過去にも参考になりそうなミステリ映画を取り上げています。いくつかフィードバックすると、
映画のここを見ろ!その2(主人公の秘密を明らかにする回想シーン)『スリー・ビルボード』
その3(謎の解明と、消えた花婿を探すミステリー構造)『ハング・オーバー!』
その5(孤独な麻薬の運び屋の旅)『運び屋』
その11(絶妙な伏線で運ぶホラー)『ゴーストランドの惨劇』
その15(サスペンスで括る群像劇)『ホテル・ムンバイ』
その17(主人公のハンデと空間限定サスペンスの古典)『暗くなるまで待って』
その19(二転三転する家族物語)『パラサイト 半地下の家族』
その36(名作刑事物のいいとこどり)『21ブリッジ』
その41(実は凄腕という秘密のナーメーテーター映画)『ドント・ブリーズ2』
その47(ジャンルミックスによるパラドックススリラー)『アンテベラム』
その50(ぶれない悪女の魅力炸裂)『パーフェクト・ケア』
その65(徹底アクションと強い敵役)『犯罪都市 THE ROUNDUP』
その73(羅生門様式でミステリー要素)『怪物』
その81(ホームドラマをミステリ?で引っ張る)『落下の方程式』
などなど。ぜひぜひ参考にしてほしい。
さて『おんどりの鳴く前に』。珍しいルーマニア映画で、若手のパウル・ネゴエスク監督作。たった一人の警察官イリエ(ユリアン・ポステルニク)がいる片田舎の村には、事件らしい事件もなく日々平穏無事。イリエは警官を辞めてうち捨てられた果樹園を買い取って、経営する計画を立てている。
そこに若い新人警官ヴァリが配属されると、村人の一人が斧で殺されるという事件が起きる。早々と犯人がイリエに「自分がやった」と名乗り出るものの、そのまま秘匿されてしまう。村が平和なのは、実力者である村長と教会の司祭が、村人の関わるあらゆる揉め事や はかりごと を牛耳っていたためで、イリエにも見て見ぬふりをするように命じていたからだ。
しかし、警官になったばかりのヴァリは、正義感に燃えて捜査を行う。上司であるイリエは、村の平穏を守るためにヴァリを止めようとする。
この後の展開は見てもらうとして、この概要のように主人公のイリエは、ひたすら事なかれ主義のクソ野郎です。有力者である村長や司祭らの悪事には眼をつむり、保身のために部下の捜査もストップをかけようとします。本来の警察官の役目なんかどこかに放り投げて、長いものに巻かれていく。
この主人公の行動なりを見ていて思うのは、まさに今の世の中。近頃の世相やスキャンダル(モリカケサクラや裏金問題、アメリカ大統領選などなど)を挙げるまでもなく、不正や悪事に、多くの人が見て見ぬふりをするようになっていないか、ということ。
さて、今回の「ここを見ろ!」は邦題ともなっている「おんどり」です。
トップシーンが、軽トラックの荷台から一羽の鶏が逃げ出す(おっこちる)場面で、この鶏が再三映ります。イリエ自身を被らせているのですが、実は『新約聖書』の「マタイによる福音書」からの引用とのこと。
イエス・キリストは、第一の使徒ペテロに「あなたは今夜、鶏が鳴く前に、三度私のことを知らないというだろう」と予言する。そしてキリストの処刑前に捕縛を怖れたペテロは、保身のため三度「知らない人だ」と証言してしまう。
この逸話をモチーフとすることで、本作はただのミステリーではなく、人間の根源を掘り下げるテーマを際立たせる役割としています。
「モチーフ」というのは、作家が作品を描くための「動機」とか「動因」といった訳され方をしますが、その作品を「象徴する何か」といった方がいい。本作の場合は、籠から逃れてあちこちと歩きまわる一羽の鶏こそが、使徒ペテロでありイリエ自身といえる。
若い部下が村人に痛めつけられたり、自身が慕う被害者の妻までも酷い目に合うのを目の当たりにしたイリエは、次第に(ペテロがそうであったように)変化していきます。そして、衝撃のラストシーンへと物語は展開し、観客にさまざまな感慨を与えて終わります。
このミステリーの構造やテーマ性、現代性、そしてモチーフを据えることで、どこにもない物語とできる。そうした作りをぜひ参考にしてほしい。
▼YouTube
カルチュアルライフ
【予告】ルーマニア映画『おんどりの鳴く前に』
【基礎講座コースについて】シナリオの技術が分かれば映画が何倍も面白くなる!
シナリオ・センターの基礎講座では、魅力的なドラマを作るための技術を学べます。
映像シナリオの技術は、テレビドラマや映画だけでなく小説など、人間を描くすべての「創作」に応用することができます。
まずはこちらの基礎講座で、書くための“土台”を作りましょう。