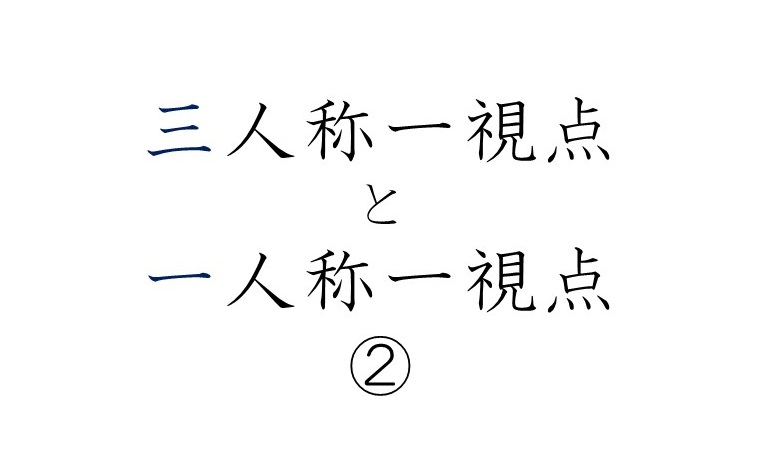シナリオ・センターでは、ライター志望の皆さんの“引き出し=ミソ帳”を増やすために、様々なジャンルの達人から“その達人たる根っこ=基本”をお聞きする公開講座「ミソ帳倶楽部 達人の根っこ」を実施しています。そのダイジェスト版を『月刊シナリオ教室』(今回は2014年2月号)よりご紹介。
ゲストは、文学座さんの、当時の新作舞台『未来を忘れる』(作=松井周 上演:2013年10月18日~11月1日)の演出家・上村聡史さんと、同舞台に出演中の俳優・加納朋之さん。それぞれの立場から、脚本とどう向き合って舞台を作り上げていくのかをお話いただきました。
作家と演出家別々で
〇上村さん:当劇団は久保田万太郎さん、岸田國士さん、岩田豊雄さんの3人の劇作家が立ち上げた劇団です。お堅いものばかりやっているという印象があるかもしれませんが、文学座には2つの軸があります。大衆路線を狙う「本公演」と、先鋭的なものや海外の翻訳劇、日本の劇作家の書き下ろし新作を上演する「アトリエ公演」。
「アトリエ公演」では、近年岩松了さんや平田オリザさん、今回『未来を忘れる』という作品を書いた松井周さんなど、新しい文体に取り組んでいこうという試みで行っております。文学座は格式がある、と思われがちですが、この「アトリエ公演」で活動の幅を広げています。
新作上演の場合、企画立ち上げには様々なパターンがあります。例えば井上ひさしさんの場合、自らが主催者として「こまつ座」というプロデュース集団を立ち上げ、そこで必ず井上さんの作品を上演するという形を取られています。これは劇作家先行型、劇作家の創造性を一番に考えた企画集団のように思います。
文学座の場合は、演出家や俳優が「こういうものをやりたい」と自分たちが原案を築き、作家に新作を発注するという、現場視線の立ち上がり方が多いです。僕はアトリエ公演の演目を決める委員をやっているのですが、書き下ろしの場合「日本の劇作家が今この時代をどのように意識しているのか、その意識から紡がれる言葉を聞きたい」という気持ちで、毎年必ず現代の作家の新作を企画しています。
近年の演劇は、「書くだけ」という作家は少なく、書いて且つ演出するという方がほとんど。ですから今の演劇界には、作と演出を分けて演劇作品を作るという感覚がない。
でも文学座はこれをずっとやり続けています。演出家の視点を作家に投げかけることで、持っている以上のものを引き出してもらおう、化学反応によってより豊かな戯曲を書いてもらおうという狙いです。
新作の立ち上げ
〇上村さん:松井周さんは、非常に実験的な作風の作家さんです。演劇には、起承転結がしっかりとある物語を重視した近代演劇と、50年代フランスのサミュエル・ベケットという劇作家が創り出した、俳優の身体性こそが舞台のメインとなる現代演劇の2種類に大別できますが、松井さんは現代演劇寄りで、物語を離れて俳優のパフォーマンスを追求する方なんですね。
文学座は、物語の方を取り組むことが多く、むしろそうでないことに挑戦しようということで、松井さんにお声を掛けました。2年前に上演を決定し、初めのうちは2カ月に一度くらい、1年前くらいからは1カ月に一度という割合で、打ち合わせを重ね、アイデアを出し合い、初稿が出て、その後7稿まで書き直してもらって決定稿になりました。
芝居の場合は、大体40日間稽古をします。ホン読みをし、立ち稽古をして、本番に向かっていきます。稽古をする中で、俳優から「ちょっとこのセリフは言いづらい」とか「ここは辻褄が合わない」といった意見も出てくるので、「現場でこういう意見が出ていますが、どう思いますか?」と作家に投げます。
すると「ここは変えなくて大丈夫」「ここは変えましょう」などと、キャッチボールをしながら精度を上げていきます。作家と演出家の価値観がぶつかり合うこともありますが、自分ひとりだと思いもよらない第三の価値観が生まれる時もあり、作品をより息づく活性剤になります。
ドラマや映画では7稿というのは当たり前かもしれませんが、演劇の場合は逆に「一発出し」の人もいるようです。初稿を変えないという。そういう場合は、演出家がその作品を気に入らないと大変なことになります(笑)。
あと、作・演出を同じ人がやる場合、半分なり3分の2くらいを書いた時点で稽古に入り、俳優の声を聞いた上で残りを書き上げるというスタイルの人もいます。
僕は一昨年、文化庁の在外研修で1年間イギリスに留学して、ロンドンにあるソーホー劇場という新人の劇作家を養成に重きを置いた劇場で研修しました。イギリス演劇は近代演劇の流れ、物語性が主流です。
そのため作品における劇作家の位置は第一位なのですが、戯曲の言葉は“俳優の身体を通して成立するもの”という紙面上だけでは成立しない、演劇ならではの台詞の効用を熟知しているので、例えば初めに6ページ書けと、上演の3年前にプロデューサーから言われる。
そして俳優を呼んで、その6ページの稽古をし、意見を出し合って、「ここはこうした方がよい」とか「こういう物語にしよう」と話し合う。そして上演2年前には台本の半分、1年前には一稿、そしてどの過程にも俳優を呼んでディスカッションし合う。このようにして劇作家を軸としながらいろんな意見を取り入れながら作品を創っていきます。
日本の演劇でも、そういうやり方を踏襲している劇団もあります。演劇の場合は、映像に比べてバイアスが多くないので、本当に自分たちのやりたい作品、書きたい作品を通せる環境なのかなと思います。
そういった意味でいうと俳優の性格、仕草や息遣いをアイデアの主軸にして書いていく「当て書き」という技術は、いかに違和感なく台詞を俳優が感覚化してしゃべるかということを作家が意識しているので、現場としてはとても助かりますし、書きたいテーマもありながらもどこかで俳優のことを考えて書いてくれる作家は、とても信頼できます。
俳優の台本の読み方
〇加納さん:今回私が出演した『未来を忘れる』という作品は、どちらかというと実験的な台本です。こういう作品を俳優が最初に読む時、俳優はどうやってキャラクターを作っていくのか、まずお話したいと思います。
私の場合は、セリフの語尾を気にします。「なんでこんな語尾を使うんだろう」という点にすごく時間を掛けました。
恋人に対する言葉が、敬語からそうでない言い方に変わった瞬間、「なぜここで変わったんだろう」ってことを、みんなで話し合います。役を作る俳優としては、作家の意図を探り、深く読みとろうとするものなんです。
台本を読んでみて、人間性が通ってないと、「エッ?」と思ったりします。皆さんがシナリオを書く時に、自分の言いたい言葉をどの登場人物に言わそうかな?ということを考えると思います。
でも、言いたいことばかり書いていると、すぐに終わっちゃいます。その間をつなぐ無駄話であったり、言いたいことへ話を持っていく会話、それが大事なんです。
私も自分でホンを書く時には、伝えたい方向に自然に持っていきたい。普通の世間話から、いつの間にか本題に入っていくというような作り方をしています。
不条理劇を得意とする作家の別役実さんが言っていたことですが、Aさんが「〇〇さん、風邪ひいたみたい」と言います。するとBさんがCさんに「〇〇さん、具合悪いみたい」、そしてCさんが「入院しているみたい」、Dさんが「亡くなったみたいよ」という風に、少しずつズレていく。
その話が本人のところに返ってきて、「え?亡くなってたんじゃないの?」となる。人に話をする際に、少しずつ盛っていったことが、いつの間にか違う話になってしまう。そんなことが、自然な形でホンにできればと思います。別役実さんはこういうことが実に上手くて、非常識な人物がいつの間にか常識的になっている……というような作り方をすることが多い。
それからタイトルも重要です。『未来を忘れる』、これもいいタイトルです(笑)。いろんな意味に捉えることができ、想像力を働かせられる。こういう仕事では想像力が一番大切だと思います。
私が先日書いたホンでは、ある飲み会でアイデアが生まれ、その勢いでバッと書いてしまった。ただ、そのアイデアひとつだけではコントにしかならない。ですから図書館で本を何十冊も借りてきて、面白そうなエピソードをピックアップしました。
しかし最後がなかなか決まらない。話をどう終わらせるかは一番大事なところですが、これが決まらなくて困ってしまいました。本番の日は近づいてくるのに、書けない。書けない時って、無理しても書けないんですよね。気分転換でテレビを見たりお風呂に入っている時などに、いわゆる「降りてくる瞬間」がやって来る時もあるんですよね。
書き終わると、何度も何度も読み直して、役が通っているかどうかを自分で演じてみてチェックします。現場にホンを持っていって、役が通っていないと、俳優たちから、特に女優陣から文句を言われます(笑)。
セリフで情報を伝えることも必要ですが、舞台上で存在する俳優にとっては、役としての何かドラマが必要なんです。役のバックボーンが欲しい。どういう環境で生きてきて、どういう人なのか。だからこういう言葉を吐くのだ、と。
「役が通っている」ということは、普段周りから「面白い」って思われている人が、急に暗いことを言ったら、そこに何か意味が生じます。何か抱えているんじゃないかとか。しかし、まったく意味のない場面で暗いことを言ったりすると、この人はそんなこと言わないんじゃないかと思ってしまい、稽古の時に苦しみます。そういうセリフを書くのならば、意味を持たせてほしい、ということです。
舞台の場合、その場から人物をどける作業も必要になってきます。部屋にいるシーンで、誰かがいると話が出来ない、というシチュエーションがあったとします。どうやって邪魔な人物をどけるか。トイレに行く、休憩にする、携帯が鳴る。そしてその人がいなくなった直後に、何かが起きるとかね。
AさんとBさんが「嫌い」という感情から最終的に「好き」になるというストーリーがあるとしますね。その間の心の揺れとか、気持ちが変わっていく瞬間を描くところがみんなにとって楽しい。そこを大事にしたらいいんじゃないかと思います。
演出家の台本の読み方
〇上村さん:今回の『未来を忘れる』という作品は、「抽象的な話を書いてください」と、作家の松井周さんにオーダーして成立しました。ひとつの場面で展開されるシチュエーションコメディではなく、現代日本の危機感をあぶりだすような作品を、イメージの断片集のようなものを書いてくださいと。
そうしたら、ものすごい設定で書いてきました。SF作品で、ある小動物のエキスを人間の体内に入れて生き延びるという話。そこに夏目漱石の「夢十夜」を引用し、感情という人間にしか持ち合わせない厄介な産物をモノ目線で描くという。
僕は、俳優の身体を魅力的に見せるような文体を構築することはできないだろうかと松井さんにお願いしました。コンテンポラリーダンスの要素も入れながら芝居を作っていったんですが、台本をもらってから芝居を作り始めたのではなく、書いてもらっている最中から演出も込みで一緒に考えていったという感じです。
今回の芝居はシーンが24あります。芝居にしては多い。戯曲では、起承転結の4幕構成が鉄板なんですが、今回は24シーン。しかし24シーンというのを単純に場面が多いと捉えるのではなく、主人公の見ている景色が24シーンあるだけで、実際の気持の流れは4幕構成のような流れではないのかと。そのようなことを作家に話すと「なるほど、上村さんがそういう流れを創るならば、僕はこういう文体にしようと思う」というような打ち合わせを重ねました。
逆に新作ではなくて、元からホンがある場合は、徹底的に戯曲を読み込みます。この作家は何を書こうとしたのかを考える。例えば来年はサルトルの『アルトナの幽閉者』という59年に書かれた作品をやります。サルトルの書いた言葉の中から、現代に通じる普遍性はどこにあるのか、59年という時代と現代の接点は、ドラマツゥルグの古さを何をもって克服すればいいのかなど。
こういった既存作品の場合は作家が書いた言葉の裏にどんな意味が込められているのかを徹底的に読み込むほかないんですね。そこまで考えないと、わざわざ既存作品を今上演する意味はありませんし、何よりも作家に失礼な気がします。
書くという作業はとても大変です。血反吐を吐く思いで書いているのを知っているので、それに報いるためには読み込むことしかできない。そういう真摯な思いで取り組んで、作家の言葉を活かしていきたいと思っています。
キャスティングと役作り
〇上村さん:キャスティング、これが作品の勝敗を決めるところかなと思いますね。新作の場合、一番嬉しいのは、作家とキャスティングの相談ができること。演出家としてラッキーなことです。それはもしかしたら僕の演出方法に関係しているのかもしれません。僕は俳優の持ち味をとても大事にするタイプです。
皆さんも、イメージキャストはどんどん言った方がいいですよ。「こういう人を想像して書いた」とか。昔のスターでも、自分の身近な人でもいい。それを伝えることで、読む側も「こういう人なんだ」とわかることがあります。
小説と違って、舞台、映画、ドラマは俳優の声を通しての表現です。僕は今年、劇団協議会が主催する『日本の劇戯曲賞』の審査員を担当したのですが、「このキャラクターって何?」という意見がよく出ます。
つまり物語は面白いのに、人間が生きていない、人間に面白みがない。反対に物語は面白くなくても、登場人物がイキイキしていてる、そういう作品の方が惹きつけられますね。特に舞台では人物造形がとても重要ですから。
〇加納さん:俳優は台本に書いてあることを、自分や演出家のフィルターを通して、生きた人間として作り出すというのが仕事です。「あの人怖いな、優しいな」というくらいのイメージは作れますが、あまり役に寄せ過ぎると、わざとらしいというか、「それっぽい人を演じている人」になってしまいます。
私は、役をなるべく自分の感覚に引き寄せるようにしています。つまり、その役の言葉・判断は、必ず自分の中にあると信じる。「ない」と思っても、自分ならどういう選択をするかなと想像する。できるだけ自分の中にあるものに寄せてくるようにしています。
ですから皆さんが書く時には、類型的にキャラクターを作ろうとするのではなく、先ほど話に出た「人間を通す」ということをしていただくと、俳優としては感情を作りやすい。人殺しをする人物を演じるとして、人を殺した経験はなくても、殺したいと思うに至る感情を描いてもらえば、役を引き寄せられるという気がします。
自分ではそんなに意識していなくても、ホンが違えば、口調や言葉遣いも変わってきますから、「今回は新しい部分が見えたね」と言われることもあります。作品に自分の持っているものを出していく、その中で自分が変化していって、普段他人に見せていない新たな面が引き出されることはあると思います。
面白い脚本とは
〇加納さん:今、漫画原作の映画が結構ありますよね。発想力がぶっ飛んでるとか、漫画は絵コンテのようなものだから、製作者がイメージしやすいというのがあるのかな。シナリオとして読みやすいホン、特に導入部がわかりやすいと、食いついてくるのかなと思います。
『未来を忘れる』は、時間が飛んだり、場が融合したりするので、どちらかと言うと特殊なホンといえるかもしれません。こうした飛び道具だけではお客さんに飽きられてしまいますが、ベースにしっかりとした人間描写があれば評価につながります。
〇上村さん:ある熱さや、何かに対して「自分はこう思う!」という志しを感じたいですね。
それをお客さんにどう提示していくかというテクニックも必要ではありますが、その熱い想いは常に持っていてほしいなと思います。
「私は生きていくうえでこれだけは譲れない」とか、ちょっとキナ臭いですけど、そういう気持ちが人を動かす原動力になる。先程の戯曲賞の応募作品の多くが3.11を題材にしたものでした。心意気はいいのですが、それを新聞記事でもよめるような批評的な視線だけで描くのではなく、文芸表現だからこそ可能な、観客を驚かすような作家自身の価値観を提示してもらいたいなと思います。
日本では、演劇というとマイナーですが、ニューヨークにしてもロンドンにしても、映画スターと言われるほとんどの俳優は国立の演劇学校出身なんですよね。演技のベースは演劇にあるということです。以前、井上ひさしさんが、「ギリシャ悲劇から現代劇まで、名作と言われる戯曲を年に100本、5年間読み続けたら500本。そしたらキミは大劇作家!」とおっしゃっていました。
それだけ先人が残した作品から勉強するものは多々あるということなのでしょう。皆さんもぜひ積極的に戯曲を読んでいただければと思います。俳優が声を出して喋るという点では、映画も演劇も同じですからね。
〇加納さん:作家も俳優も、表現して、見てもらって、初めて評価される仕事です。俳優がいくらテレビで主役をやりたいと思っても、使ってもらわなきゃ意味がないのと同じで、シナリオを書いたとしても、どこかで人に観てもらうということが必要なのです。
かつての三谷さんや宮藤さんのように、自身の劇団で上演したものをテレビ関係者が観に来て、面白いと思ってドラマなどに起用するケースが増えています。都内では毎日すごい数の公演が行われています。
それだけ表現する場があるわけですから、劇団に脚本を提供したり自主公演したり、いろいろな手段で経験してみることが必要かなと思います。「面白くない」とか批判を受けることもあるでしょうが、それが成長につながっていく。
日本演劇界の課題
〇上村さん:僕の場合、作家には必ず稽古を見に来てもらうようにしています。「見ていて何か違うと思ったら、言ってください」とお願いします。そうすることで作家のイメージから離れないようにする。
僕はとにかくいろんな人の意見を聴いて、稽古で試すことにしています。自分が言いたいことは、適切なタイミングを見計らって言う。演出というのは、現場の雰囲気をつかんで、その瞬間瞬間を見極める能力が必要。そうやって基本的に話し合いを重ねるというスタンスで演出しています。作家も書くだけではなく、演出家や俳優とクロスオーバーしていくことが大切だと思います。
〇加納さん:飲みの場で「このセリフはちょっと」と意見を言ったりすると、翌日書き換えてくれる作家さんもいます。でも、直した通りにやっていると、どうも丸くなってしまって、作家の言いたいことが薄まってしまっていることに気付きます。
作家として、変えてもいいなと思うところは変え、粘った方がいい場所については「ここはこういう気持ちで書いたんです」と主張した方がいい。波風の立たない、皆にとって心地いいホンというのは、甘いものになってしまう恐れがあります。
作、演出、俳優がうまく話し合える現場が、一番いい現場。各パートが力をつけ、それが融合すると、いい作品ができるんじゃないかと思うので、皆さんもぜひ頑張ってください。
〇上村さん:ここ2~3年、古典演劇の再演が非常に多くなっています。大きなスケールの新作を書ける作家が少ないのが、今の日本演劇界の課題かもしれません。薄っぺらい時代と共に、表現も薄っぺらくなってしまっているような気がします。
もちろん表現は時代を映す鏡ですから、致し方ないような気もするのですが、やはりドラマは感情の起因によるものだと思います。こんな時代だからこそ、埋もれがちなパッションを掘り起こし、それをドラマに転化してもらいたい。枠に収まることのない人間の“感情=パッション”をどう描くか? やはり突破口はこれに尽きるかなとも思います。
書く作業というのは自分の子供を産むような大変さがあると思います。でも、「自分はこれがあるから書くんだ」という信念を持っていれば、すごいものが出てくるのではないでしょうか。それを信じて書き続けてほしい。皆さんのご活躍を期待しています。
出典:『月刊シナリオ教室』(2014年2月号)より
※加納さんが【■俳優の台本の読み方】でお話いただいたことは、弊社実施の戯曲講座でご協力いただいた青年座さんの役者の方々も仰っていました。その模様はこちらからご覧ください。
※文学座公式サイトはこちらからご覧ください。
〈採録★ダイジェスト〉THEミソ帳倶楽部――達人の根っこ
「演出家、俳優の立場から考える脚本力」
ゲスト:上村聡史(文学座 演出家)、加納朋之(文学座 俳優)
2013年10月25日採録
★次回は7月23日に更新予定です★