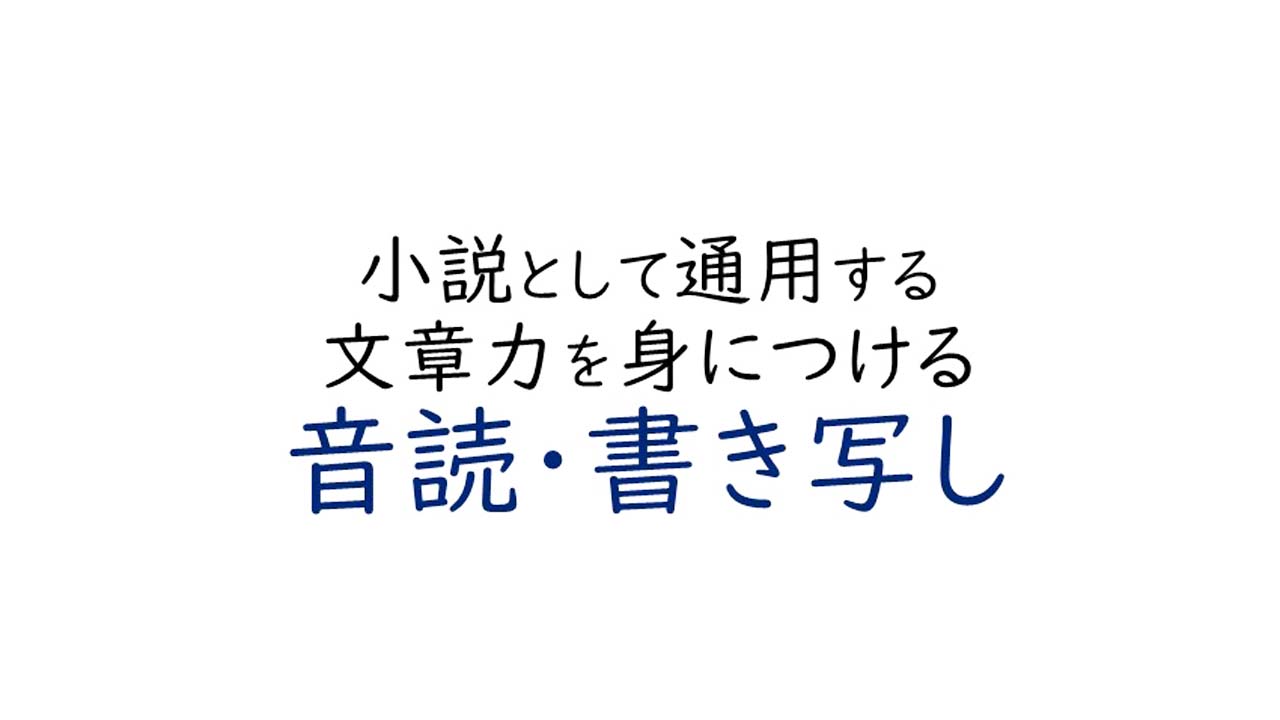アニメーションのキャラクターの描き方
〇西村さん:僕と坂口さんの出会いというのはシナリオ・センターでしたね。
〇坂口さん:私が『かぐや姫の物語』という高畑勲監督の映画脚本を書かせていただいた時に、最初にシナリオ・センターに問い合わせてきたのが西村さんでした。その時のご縁で今回『メアリと魔女の花』もお声掛けいただきました。
『メアリ~』は、米林宏昌監督と西村義明プロデューサーとの3人で打ち合わせをしていました。スタジオポノック設立前のときは、ずっと喫茶店で話していて、喫茶店の人に追い払われながらやってましたよね(笑)。
『かぐや姫~』のときは高畑監督とですが、『メアリ~』も少数でじっくりやることができてよかったです。
〇西村さん:脚本と演出との関係って、非常に曖昧なものだと僕は思っています。
アニメーションの場合、絵で描くという自由と、一方で制約もある。才能豊かな役者さんが演じて、優れた演技によって傑作と化した実写映画はあるでしょうが、アニメーションでは微細な芝居を前提に脚本は書くのは極めて難しい。絵描きが表現できる芝居かどうかの判断が根っこにあって、だからこそ、脚本家と絵描きの共同作業は大切だと思っています。
今は脚本家と映像の作り手が分業で脚本を作るケースがありますが、それをしていたら、今回の映画は出来なかったと思います。
〇坂口さん:脚本と監督が一緒だから成立したという映画はたくさんあると思います。私の場合は脚本だけなので、どこまで監督とコミュニケーション取れるのかというところがあって、全然違う風にとられることもありますし。
今回のアニメーションについては西村さんに言われて、なるほどって思ったことがあります。
思いをこめた「……」ってあるじゃないですか。役者さんだったら、そこでしっかり思いをこめてくれて、すばらしい演技をしてくれると思うんですが、これを何ヵ所も書いた時に、西村さんに「坂口さん。これ、書いてもアップになるだけです。アニメの線が太くなるだけですから」って言われました。
確かにって思いました。アニメのキャラクターにそこまでの演技というのは要求できない。その代わり何か動きというかアクションで見せていくしかない。そこが一番違うなって思いました。感情をこめさせるのが難しいですね。
〇西村さん:基本的には2Dのアニメーションというのは、紙に書かれた絵です。紙に書かれた目と口と鼻。そういうパーツ、記号の集積で人物造形をしている。
そこに感情移入させたいと思った時に、ただ人物の佇まいだけを見せて、「ほら、可哀相でしょう」と言っても、記号を超えたものには成り得ません。極めて写実的なキャラクター造形を成した場合は別として、人物造形そのもので繊細な人物を設定するのは基本的に難しいんです。
例えば、実写で夏木マリさんがボサボサ頭でたばこをふかしていたら、「ああ、こういう女の人、田舎の床屋さんとかにいそうだな」とか、具体性をもって見せることができるかもしれませんが、アニメーション映画の場合は、そうはならない。それっぽい単純な記号的人物になってしまい、面白みに欠けてしまう。
豊かな人物を表現するには、人物を豊かたらしめる物語状況を設定するしかないんです。ある状況に対して、その人物はどう反応するのかということで性格を描くわけです。逆説的にいうと、状況が変化しないものは、なかなかアニメーション化が難しいと思っています。モノローグとか説明セリフで伝えるしかないから。
〇坂口さん:それにアニメーションが耐えられるかってことですよね。
〇西村さん:脚本技術の習得段階で「私は、あの時、あの人のことを思っていた……」ってモノローグばかり書いていたら、授業ではダメを出されますよね。様式としてはあり得ますよ。モノローグを多用すると様式が生まれるってことはあります。でもモノローグに頼って脚本を書いたら、たぶん、皆さん、すぐにダメだって言われると思います。
今回『メアリ~』も、どうしようもなくて独り言を使った部分がありますが、独り言っていうのは基本やりませんよね。「あー、この水、冷たい」って言うとか。そういう独り言を言っている人いますけど、喫茶店とか行くと(笑)。
でも普通の人間が電車に乗っていて「あー、今日も満員」って言う訳ないってことです。でも今日も電車が満員で、その人が満員電車をいつもどう思っているか、その状態を伝えるには、どうしたらいいのか。
『思い出のマーニー』という原作では、主人公がほとんどしゃべりません。内面に問題を抱えていますが、人物の心情はセリフではなく、地の文で語られます。
原作中に、主人公が義母と和やかに話したあとに、急に腹が立って、ドンドンドンってすごい勢いで階段を駆け上がっていく描写があるんですが、こういうのが厄介です。原作では客観説明で主人公側の理由を語るんです、地の文で。それを映画で芝居だけで表現したとしたら、何がなんだかわからなくなる。
〇坂口さん:心の中は描けないですから……。
〇西村さん:さっきまで話していたのに、なんで急に荒れ狂っているんだろうってなる。原作は心理的な病を扱っていて、そういう女の子が自分を取り戻す話です。といっても、いきなり荒れて階段を登っていったら、観客は置いてけぼりをくらって、嫌悪すら抱きかねない。
共感できなくて嫌いになった人物を、途中から好きになるっていうのは、それが主眼の映画なら挑戦しようがあるけれど、それにしたって、状況が変化しないのならば、「実はわたしは」とモノローグや説明セリフを使うことになる。「実はこの子は」と観客が理解を深める物語内の機会が設定されないとすれば。
だから『思い出のマーニー』が映画化されるとなったときに、一瞬どうしようと思いました。この子はどこかに行っても状況が変化する訳じゃない。何が問題なのか自分でも言わない、自分でもわかっていない。多くの場合、思春期の問題って、何が問題なのか自分すらわかっていないことが多いから。
〇坂口さん:答えがないからこその悩みみたいなことですね。
〇西村さん:児童文学でも、とりわけ思春期というのは作家の好奇心を駆り立てて、多くの物語があります。
思春期の葛藤って特徴がありますよね。自分はどうして生きているんだろうとか、ひとはなぜ死ぬんだろうとか。自分はどこから来て、どこへ行くのだろうとか。アイデンティティの問題に直面しているわけです。それが思春期の象徴なのかもしれませんけど、それをどうやってアニメーションで表現したらいいか。
児童文学ではよく〝影〟が出てくる。何かに追われるんです。影に追われたのが『ゲド戦記』で、『バケモノの子』って映画にも影が出てきますよね。もうひとりの自分を出して、その自分との対峙の末に自己を確立させるべく描く。他と隔絶された自己との対話の末に、成長し、解放へと向かっていく。『思い出のマーニー』も、もう一人の自分との出会いでもある。
思春期って、心理的に引きこもったり、内にこもる場合が多い。お母さんにも言わないし、親父にも何も言わない。無口になる。内面が分からない。だからこそ挑み甲斐がありますが、思春期を扱うのは、アニメーションに限らず、とても難しいとは思います。
〇坂口さん:アニメーションはいちばん難しいかもしれませんね。実写だったら表情だったり、ちょっとした母親との言い合いだったり、そういうもので表せるかもしれないですが。
〇西村さん:マンガの場合は術がありますよね。マンガって文字を扱うのが前提になっているので、説明として許容される範囲の心理説明ができる。モノローグは、少女マンガでは様式として確立されていますから、わからせたいことは、わからせるべく語ることもできる。