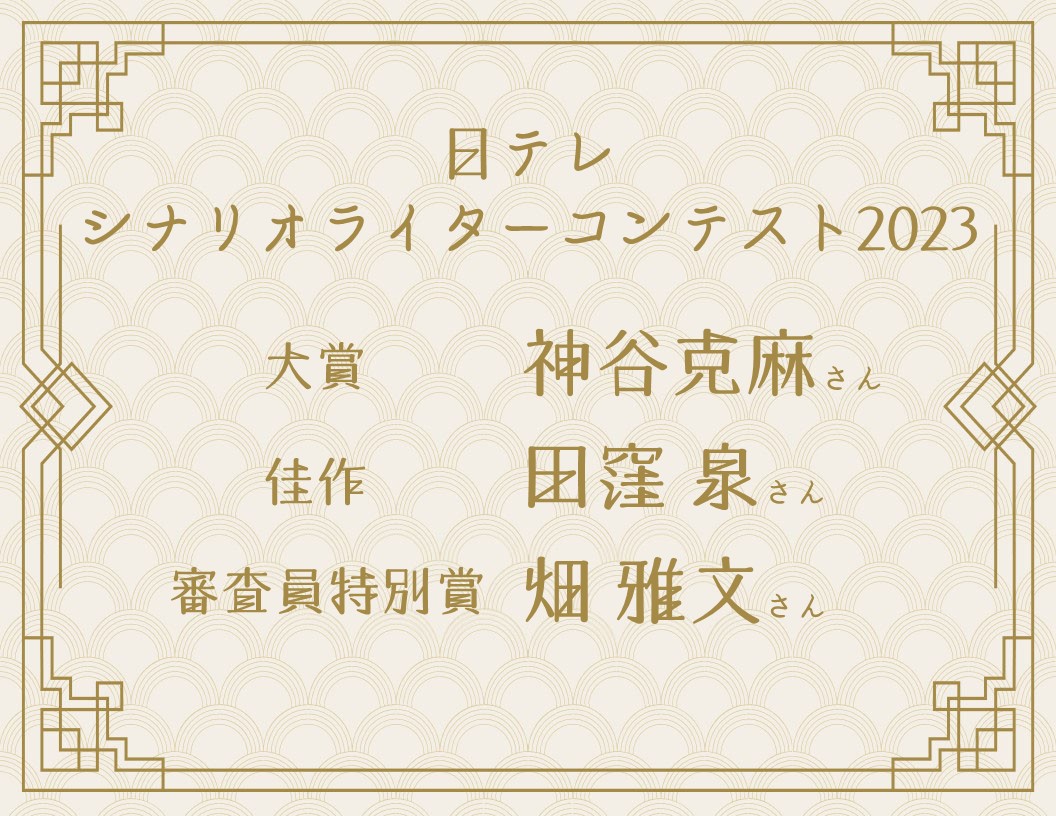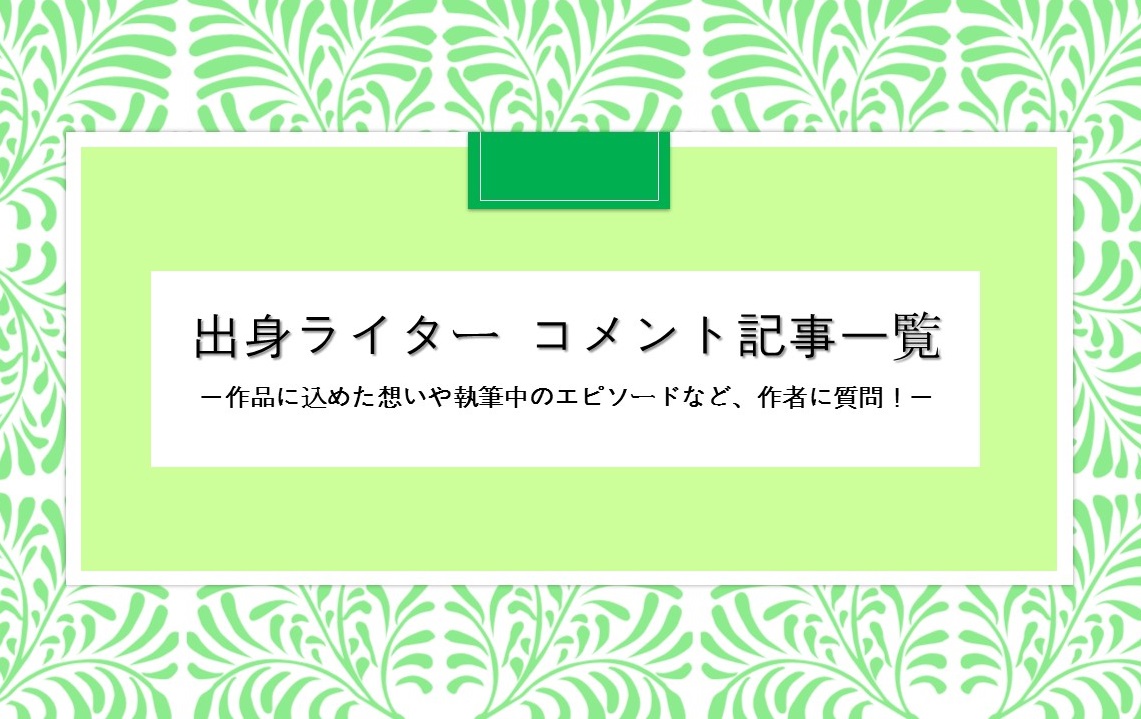脚本家でもあり小説家でもあるシナリオ・センターの柏田道夫講師が、公開されている最新映画を中心に、DVDで観られる名作や話題作について、いわゆる感想レビューではなく、作劇法のポイントに焦点を当てて語ります。脚本家・演出家などクリエーター志望者は大いに参考にしてください。普通にただ観るよりも、勉強になってかつ何倍も面白く観れますよ。
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その19-
『パラサイト 半地下の家族』
設定、切り方で、真逆になることが分かる傑作です
今、大きな話題となっている『パラサイト 半地下の家族』について。韓国映画ですが、アカデミー賞で作品賞にノミネートされています。獲るかもしれませんね、あまりの面白さとインパクトで。
ところでパンフレットには、冒頭に「ポン・ジュノ監督からのお願い」という一文があって、〝兄妹が家庭教師として働き始める以降の展開を語ることは、どうか控えてください〟とあります。その言いつけを守って、ここでもけっしてネタバレしないように書きますね。
どうして早々とこの映画についてアップしたかというと、前回取りあげたケン・ローチ監督の『家族を想うとき』(※)と比べながら見て頂きたいから。
ラジオで映画評論家の町山智宏さんが、この映画について喋っていましたが(ちなみにパンフの町山さんのレビューは、ネタバレ満載なので絶対に先に読まないように)、日本で是枝裕和監督の『万引き家族』(このコラムでは7回目に取り上げました)、アメリカでジョーダン・ピール監督の『アス』、そしてイギリスの『家族を想うとき』、そして本作の韓国『パラサイト』と、まったく内容やジャンルは違うけど、ベースに共通項のある映画が、各国で次々と生まれていると。
その共通項こそ「貧困層が置かれた現実」ということ。
その通りなのですが、今回『家族を想うこと』と比べて見てほしいのは、そうした非常によく似た構造と、真逆なアプローチ法です。
『家族を想うこと』で、ケン・ローチ監督の一貫した作風は、ドキュメンタリータッチだと述べました。ドキュメンタリーのように、登場人物たちの姿、生活をリアルに描いて、観客に〝現実〟を突きつけていく。
この作風に対して、ポン・ジュノ監督は、これでもかこれでもか、と観客を裏切る二転三転する展開を持ってくる。リアルなドキュメンタリータッチとは正反対ともいえる、フィクションを構築していく。ポン・ジュノ監督の代表作のひとつ『グエムル–感江の怪物–』がまさに典型ですが、家族の奮闘をテーマとして据えつつ、彼らが戦うのはダンプカーサイズの怪獣でしたから。
『家族を想うこと』と『パラサイト』は、両親と息子と娘の4人家族というのも同じですし、共に貧しい。社会構造ゆえにですが、そうした底辺に蠢いていて、必死に日々を送っているのだけど、そこから這い上がる道はほぼ閉ざされています。そうした絶望感が彼らを覆っている。
でありながらも、彼らはそんな不公平な社会に対して、直接に抗議の声を上げたりすることもなく、大切なことは家族を深く愛している点です。
そうしたベースは同じなのですが、ケン・ローチはリアルに徹することで、観客にテーマを突きつける。あなたと彼らは同じなんですよ、という問いかけをするために、意図的にフィクション性を除いたように描いていく。
これに対してポン・ジュノは、伏線を張り巡らせた上で、観客の予想を超える意外性を盛り込む徹底フィクションとして構築していく。
この両者の正反対のアプローチの違いを、どちらが先でもいいので、見比べてほしいのです。
もうひとつ前々回、サスペンスの教科書的な作品として『暗くなるまで待って』(これも半地下の家が舞台でした!)をとり上げましたが、この『パラサイト』のサスペンス手法も見事です。
サスペンスの定義は、〝緊張〟〝宙づり状態〟と述べましたが、それに加えて、〝意外性〟つまり観客の度肝を抜く展開が持ってこれると、おもしろさは倍増します。『パラサイト』はまさに! なのです。
それにしても、こんな韓国映画を観てしまうと、ついわが国は……と思ってしまいますが、その愚痴は今はやめておきましょう。
※「柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その18『家族を想うとき』直に訴えないからこそ「テーマ」がじわじわと伝わります 」はこちらからご覧ください。
※YouTube
シネマトゥデイ
第72回カンヌ国際映画祭で最高賞!『パラサイト 半地下の家族』予告編
-柏田道夫の「映画のここを見ろ!」その20-
『ジョジョ・ラビット』
構成はもちろん、発想としても「アンチ」で考える
今回取り上げるのは、題材としてはけっして新しくない戦争物、それも第二次大戦のドイツナチス政権下の物語ながら、今までになかった戦争映画! と思わせる『ジョジョ・ラビット』。
題材はありきたりなのに、どうして「新しい」のか? そこを考察することで、「なんだ、またかよ」ではなく、「なるほど、こういう描き方があったんだ!」と感じさせる創作のアプローチ(切り口)が見つかるはず。
この物語の設定は、ナチスドイツが戦争をしている最中に、本当は気弱なのに、祖国とヒトラーを信奉している10歳の少年ジョジョ(ローマン・グリフィン・デイビス)の物語。ジョジョは美しい母(スカーレット・ヨハンソン)と二人暮らしで、とぼけた親友のヨーキーと、時々ジョジョの幻想として現れるヒトラー(タイカ・ワイティティ監督自身)が心の支え。
ジョジョは立派な兵士になるためのヒトラーユーゲントで訓練を受けているのですが、ウサギを殺せという命令が実行できなくて、臆病者という意味の〝ジョジョ・ラビット〟とあだ名をつけられてしまう。そのジョジョが自宅の隠し部屋に、ユダヤ人の少女エルサが匿われているのを見つけてしまって……
さて、新しい切り口とはなにか? それはズバリ、アンチとしての視点者、主人公のジョジョに他なりません。
いわゆる「ホロコーストもの」は、毎年のように映画にされ、名作もたくさんあります。ナチスがユダヤ人を抹殺しようとした計画を、さまざまな視点や切り口から描く。
それらは当然ながら、被害者であったユダヤ人側から描かれます。迫害するナチスは敵側になり、絶対的優位な権力を持っている。
最たる弱者であるユダヤ人が、この巨悪にいかに立ち向かうか? そこから逃れるか? 命を繋ぐ戦いをするのか? その構図を踏まえた方が、物語として感動的なドラマが創りやすくなります。
けれども『ジョジョ・ラビット』の少年は、根っからの軍国少年で、純粋であるがゆえにヒトラーを信奉し、ドイツの勝利を疑っていない。そのジョジョが、最も忌み嫌うべき存在であるユダヤの少女と出会ってしまう。
日本に置き換えてみましょう。今の平和な時代に生きる我々は、歴史を振り返るとつい、いとも簡単な疑問を抱いてしまいます。「どうして日本人は、総意としてあの戦争に賛同し、突入してしまったのだろう?」というような。
そういう時代だったのだから、と頭で理解したとしても、誰もが「今はそうならないよな」と思っていたりします。果たしてそうか? 昨今の世相なり時代の空気を思うと恐ろしくなってきます。
そうした今はともかくとして、戦時下をユーモアを交えて描くというのも、考えるととても難しい。けれども、世の中の仕組みなりに精通していない少年の視点に徹することで、悲惨な戦時下も子供なりの感覚、思考で描けるかもしれない。
そう、この映画の脚本は、ジョジョという多感ででも純粋な少年を主人公に据えて、彼の視点から外れずに(つまり大人の理屈や思考、立場にはけっして立たないようにして)描いているところが「ここを見ろ!」のところです。
途中のある悲劇の発覚など、この映画には随所に戦時下の残酷さも散りばめられていて、テーマを鋭く観客に投げていたりもします。
それはそれとして、愛すべき少年ジョジョに声援を送りたくなりますし、彼の未来にも希望が見いだせる。
戦争を悲劇チックに描くのはいわば正統派です。それはそれで腰を据えて描きたい。反面、エンタメとしての描き方を「今までにない」切り口として描く方法を示唆してくれます。素晴らしいラストシーンも、噛みしめて下さい。
※YouTube
シネマトゥデイ
タイカ・ワイティティ監督がヒトラーに!映画『ジョジョ・ラビット』日本版予告編