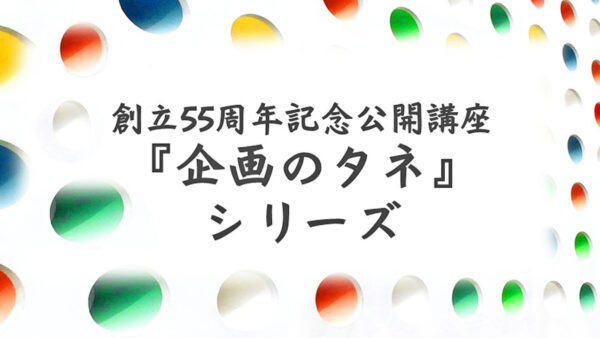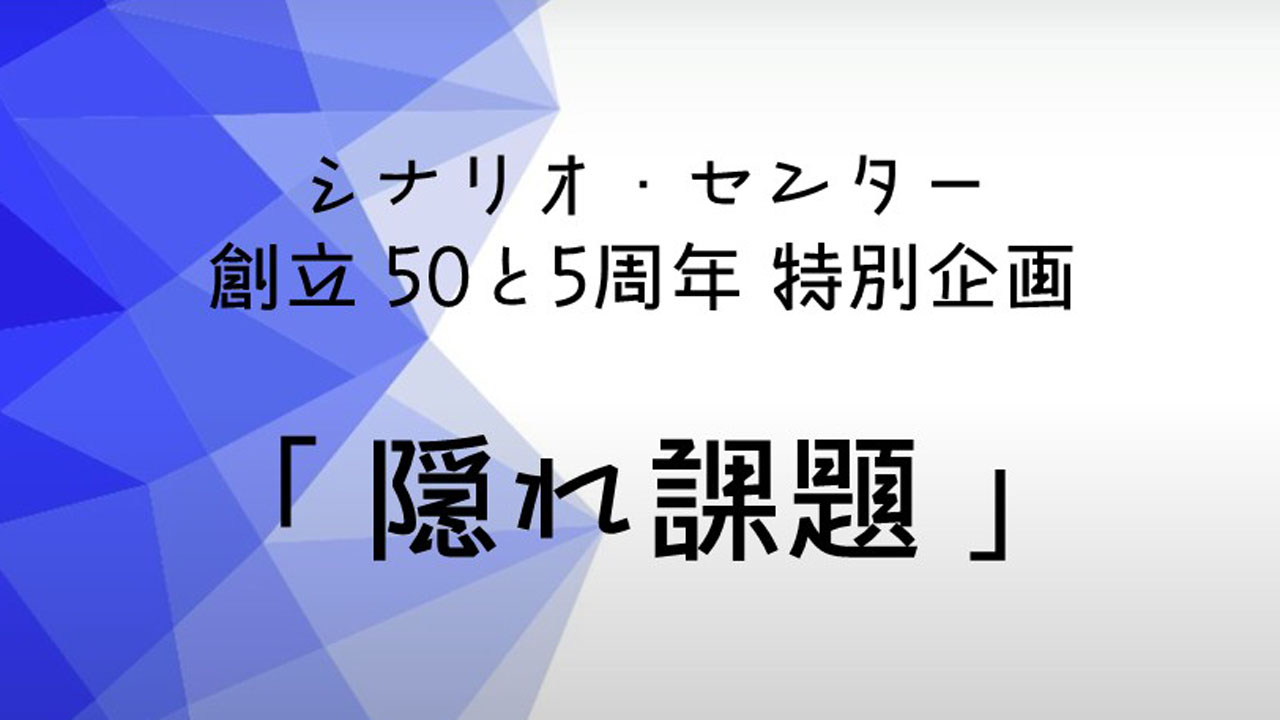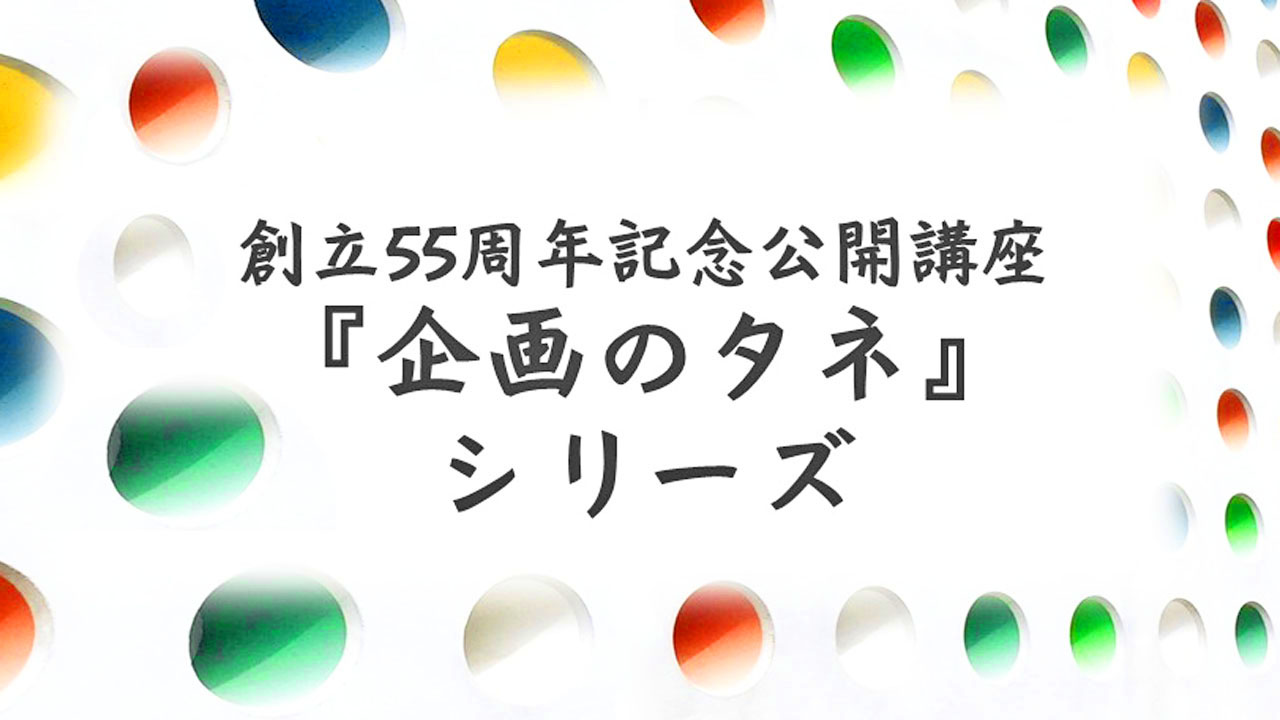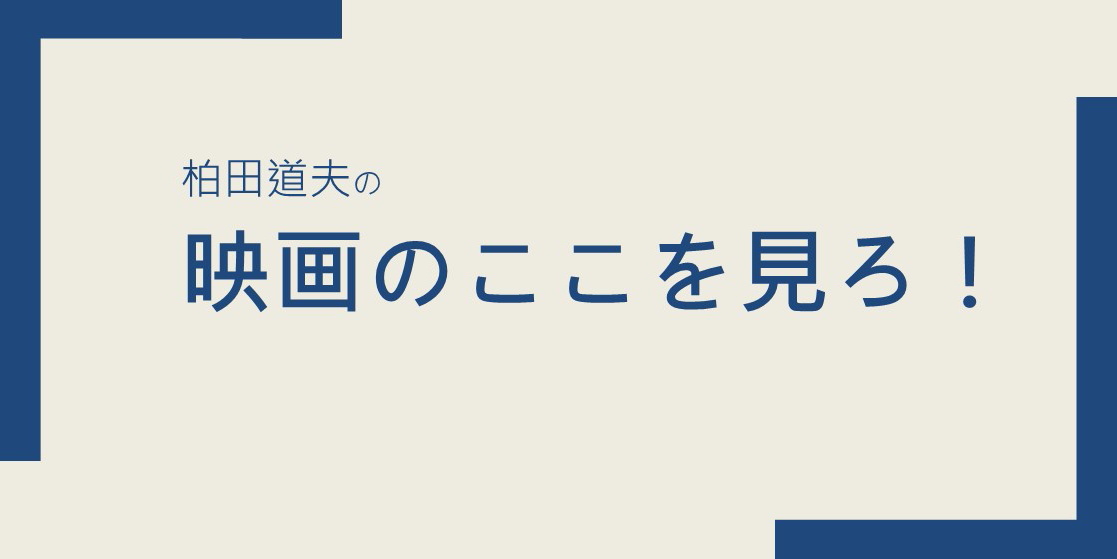シナリオ・センターでは日頃から、生徒さんに「ミソ帳(ネタ帳)を作りましょう!」とお伝えしています。
また、定期的に公開講座「Theミソ帳倶楽部」を開催。
ゲストのお話を伺い、興味を持った部分や閃いたアイデアなどを自分のミソ帳に書き留め、自分だけのネタを発酵させる場にしていただければと思っています。
今年、創立55周年を迎えたことを記念して、Theミソ帳倶楽部の新シリーズ 『企画のタネ』(全4回開催予定)を開催することになりました。しかもこの講座は「聴いて終わり」ではありません!ゲストの職業にちなんだ「企画ミニコンクール」も同時に開催。
聴講していただいた職業に合わせた企画書(※専用フォーマットを使用)を書いて提出していただき、その中から毎回1本、ゲストが選考した『ゲスト賞』を発表。選ばれた方は「長編シナリオの個人面談」を「5,500円割引」でご利用いただけます。
さらに、『企画のタネ』シリーズ全4回すべての応募企画の中から、優れた1本を企画書講座担当の柏田道夫 講師が選考。『柏田賞』に選出された方には、選考コメントと「2026年開講の企画書講座」の無料受講をプレゼントいたします。
企画のストックを作っておきたい方や企画書に苦手意識のある方。是非この講座にご参加ください!
こちらのブログでは、どんな講座なのか、“第1弾”の一部をご紹介しますので、次回“第2弾”のご参考までにご覧ください。
第1弾:カフェ経営者 編
“人間ドラマ”が繰り広げられる「柱(場所)」として、作品の中にカフェを登場させている方も多いのではないでしょうか。そこで第1弾は、東京・江戸川橋で、世界的にも珍しいネパール産のコーヒーを販売されているBIKAS COFFEEの経営者 菅勇輝さんをゲストにお招きいたしました。

ご通学で参加していただいた方には、ウェルカムドリンクとしてハンドドリップしたコーヒーをプレゼント。

いい香りに包まれながら講座がスタート。
BIKAS COFFEEの「BIKAS(ビカス)」とはネパール語で「発展」を表す言葉。「コーヒーを通して社会を作り出していく」という想いのもと、「コーヒー豆を仕入から販売」というスタイルではなく、“植樹を通して森をつくり、雇用を生み出す”というカタチを取り入れています。
講座では菅さんと企画・聞き手を担当した内藤講師のよる対談形式で進行。なぜこのような取り組みをすることになったのかという「これまでの経緯」や、実際どのように行っているのかという「実際の仕事」について等々、お聞きしました。

お話ししていただいたエピソードには、「職業モノ」を書くときに活かせるようなヒントが満載!
例えば、こんなお話が↓
〇内藤講師:シナリオ・センター研修科ゼミナールの課題にも「職業モノ」がありますし、「職業モノ」を書きたい方は沢山いらっしゃると思うのですが、こういうものを書くときに、「専門用語」を知っていると強いと思うんですよね。セリフの中に実際の現場で使っている言葉があると、より本格的な感じになりますからね。カフェ経営者としてよく使っている言葉って何かありますか?
〇菅さん:例えば、コーヒー豆の精製方法の話でいうと「ナチュラルプロセス」とか「ウォッシュドプロセス」とか「ハニープロセス」とか、いろいろ種類がありますね。コーヒー豆は、コーヒーの実の中にある、種にあたる部分なんです。実を収穫して、その中に入っている豆を精製する方法には、洗ったり、天日干ししたり、欠点豆を取り除いたり、いろいろあるんです。
また、「生活の中で様々な作物を植えながら、副業的な感覚でコーヒーを育てている」ということを僕らは「アグロフォレストリー農法」と呼んでいます。これは僕らの中では結構キーワードとして打ち出していて、別名「森を作る農法」と呼んでいます。
コーヒーは、「木陰がないと成長しない」「標高が高くないといけない」「冷たい風が届かないといけない」とか、ふさわしい生育環境の条件がいろいろあるんですけど、ネパールは標高が約1200mとそれなりにあって、国土の半分近くをヒマラヤ山脈が占めているため山の風がしっかり吹くので冷たい風も当たります。昼と夜の寒暖差が激しいというのも、コーヒーの生育条件に当てはまっています。
ブラジルとかエチオピアとかケニアとか、世界最大のコーヒー産地だと、山を切り崩して、そこにコーヒー農園を作って、農家の皆さんが「労働のために生きる!」といった感じで働かないといけない。これってすごく大変なんですよ。
それを、「アグロフォレストリー」という考え方を導入することによって、「自分たちの生活の中で、自分たちの暮らしを活かしながら、無理なくコーヒーを育てる」ということができるので、そうなると、「コーヒーの2050年問題」(地球温暖化による気候変動の影響で、2050年にはコーヒーの栽培地が激減し、コーヒーが飲めなくなるかもしれないと言われている)の解決にもなるんじゃないかなと。
だから「アグロフォレストリー」という言葉は、ネパールの暮らしの中にもあるアイデアというところで、僕らは専門用語として大事にしています。
〇内藤講師:なるほど!こういうの聞けるといいですよね。取材しない限り、こういう現場の話って聞くことができないから。
――上記は当日お話ししていただいた、ごく一部。実際にお聞きしないと分かり得ないことが沢山ありました。
例えば、「カフェ経営者」と言えば、コーヒーが大好きだからこの道に進んだのだろうな、と思いますよね。ところが菅さんによると、学生時代からネパールに学校を建てることが夢で、その活動の延長線上に今の仕事との出会いがあったと仰っていました。意外だと思いませんか?そもそものスタートがコーヒーとは全く関係ないところから始まっているというのは、あまり想像できないですよね?
この他にも、どういった経緯で植樹をすることになったのか、カフェ経営することになったのか、等々お話ししていただきました。
このようにリアルな話を聞くことで、登場人物のキャラクターを考えるときに、ストレオタイプではない発想ができるようになります。講座『企画のタネ』をキッカケに、ネットでは検索しきれない事実や、自分の想像をはるかに上回る事実を知ることができます。
そして、「知って終わり」ではなく、じゃあこれをどういう企画にするか、という練習もできるのがこの講座の“ミソ”だと思います。
今後もまた、ゲストをお迎えして、定期的にこの『企画のタネ』シリーズの講座を実施いたしますので、是非ご参加ください!
「シナリオは、だれでもうまくなれます」
「基礎さえしっかりしていれば、いま書いているライターぐらいには到達することは可能です」と、新井一は言っています。“最初の一歩”として、各講座に向けた体験ワークショップもオススメです。
※シナリオ作家養成講座とシナリオ8週間講座は、オンライン受講も可能です。
詳しくは講座のページへ